遺産に対する相続税には基礎控除が適用される
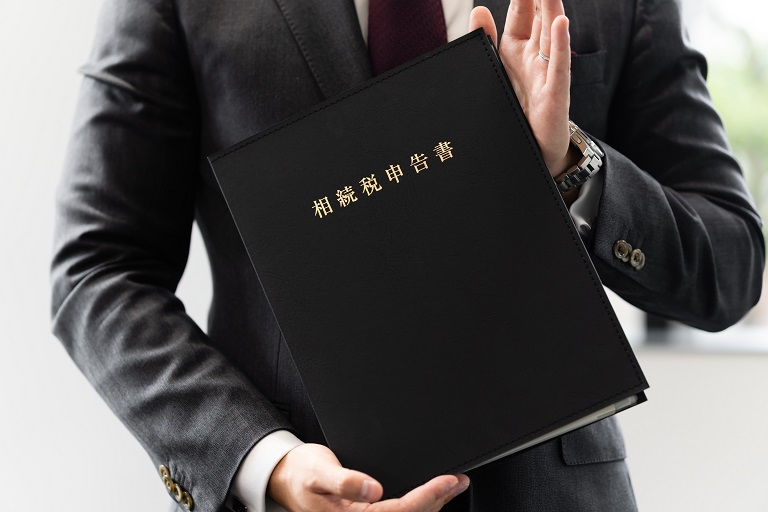
いずれ相続が発生した時のために、相続税に関する基礎控除や税金対策について考えておいた方が良いかもしれません。
誰でも起こり得る身近な問題であり、決して他人事ではないこと、そして基礎控除や税金対策について知ることが大切です。
それでは、これから起こり得る相続税の基礎控除と税金対策についてご説明しましょう。将来に備えてどのくらいの税金がかかるのか確認することが重要です。
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、相続を受ける全員が対象になる基礎控除のことです。本来相続税は相続する財産に対して課税されるものであり、財産の金額が多いほど相続税も高額になります。
しかし、相続税の基礎控除には一定のラインを超えない限り、相続税がかからないという控除制度があります。
相続税が課税されなければ申告を行う必要性もないので、できれば基本となる基礎控除額を超えないように調整するのがお得だと言えるでしょう。
もしも基礎控除額よりも遺産総額が多い場合は相続税を申告しなければならないため、注意しましょう。
また、この基礎控除額は相続人1人1人に対して計算するのではなく、一つの相続に対して計算される点も気を付ける必要があります。
それでは、相続税の基礎控除額についてご説明しましょう。
相続税の基礎控除額はどれくらい?
相続税の基礎控除額は、基本となる3000万円+法定相続人の数×600万円となります。
法定相続人の数が1人なら600万円をプラスした基礎控除額となり、2人なら1200万円がプラスされた基礎控除額になります。以降は人数が増えるたびに600万円がプラスされるので、計算はしやすいでしょう。
この方式により、遺産総額が基礎控除額の3600万円を超えていれば相続税の申告を行わなければなりませんが、超えていなければ相続税は非課税なので申告の必要はありません。
遺産の総額を算出する方法
相続税の基礎控除額を超えないようにするためには、何よりも遺産の総額が重要です。
そこで遺産の総額を計算することになりますが、遺産の総額を算出するには亡くなった日まで故人が所有していた財産を全て判明させて計算しなければなりません。
土地や建物などの不動産や現金預金といった預貯金、有価証券、生命保険の金額など全てを判明させて計算しなければならず、事前準備としてやるべきことが多くあります。
通帳や証券などが見つからない場合は被相続人の金融機関を調べて確認する必要がありますし、 生命保険に加入していたなら保険会社に連絡して死亡保険金の受け取り連絡を行いましょう。
生命保険金は一般的に受取人が指定されているので、早めに受け取るのが得策です。
そして株式運用も行っていた、もしくは株式取引を行っていた場合は、相続が発生した日の終値と時価を元に保有株数をかけて計算します。
株式によって様々な評価方法があるので、故人が扱っていた株式を確認しましょう。
そして故人が不動産を所有していた場合、不動産の価格を把握しなければなりません。不動産の価格を把握するには、固定資産税評価証明書×1.14倍となりますが、正確な価格を把握するのは難しいので税理士に相談するのがおすすめです。
税理士であれば自分たちでは分からないことも細かく対応してくれるので、遺産総額も自身で算出するよりもはるかに手軽に算出できます。
なお、相続税の基礎控除は平成27年に税制改正が行われており、基礎控除額が基本となる5000万円+法定相続人の数×1000万円だったのが基本となる3000万円+法定相続人の数×600万円に下げられているので、注意しましょう。
基礎控除における法定相続人の考え方
もう一つ重要なのは、法定相続人の考え方です。法定相続人とは民法で定められた相続権がある人のことを指しており、法定相続人として認められている人は相続を受け取る権利があります。
相続税の基礎控除に関わる重要なことなので、法定相続人がどれくらいいるかをきちんと把握することが大切です。
法定相続人は基本的に直系卑属 の子供、直系尊属 の両親、兄弟姉妹です。ただし、法定相続人には優先される順序があるので、誰が優先して相続人になれるのか知る必要性があります。(※)
※卑属(ひぞく)とは血縁関係において、その人に後続する世代にある人のこと。また、直径の尊属は、父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母など、直接の祖先の系列に当たる人を指す。
それでは、法定相続人についてご説明しましょう。
法定相続人は誰がなる?
まず、 いかなる理由があろうと故人の配偶者は、正式な婚姻関係がある場合にのみ確実に相続人になります。婚姻関係がなければならないので、事実婚関係の場合は相続人に含まれません。そして相続順位が高い子供、両親、兄弟姉妹の順番で法定相続人が決定されます。
相続順位が1位の子供は、例え両親や兄弟姉妹がいても最優先されて相続人になれます。
しかし、子供がいない場合は孫が、孫がいない場合はひ孫が対象です。子供が法定相続人になるケースは、『配偶者+子供』『子供のみ』の2パターンです。
相続順位が2位の両親は、故人に子供や孫がおらず、両親が健在の時に相続人になります。
ただし、両親が既に亡くなっている場合は、その祖父母が相続人になります。両親が法定相続人になるケースは、『配偶者+両親』『両親のみ』の2パターンです。
相続順位が3位の兄弟姉妹は、子供も孫も両親も祖父母もいない場合に相続人になります。
ただし、兄弟姉妹が亡くなっていた場合は子供の長男が法定相続人になりますが、孫にあたる子供は法定相続人にはならないので注意しましょう。
なお、『配偶者+兄弟姉妹』『兄弟姉妹のみ』の2パターンです。
法定相続人は遺言書に記載されている内容に従わなければならない
法定相続人を決める際には、故人が遺した遺言書に記載されている内容も深く関わってきます。
もしも遺言書に、本来法定相続人にならないはずの愛人や養子などに遺贈する内容が記載されている場合、必ずその内容に従わなければなりません。
遺言書の内容によっては不服申し立てを行うことによって無効になるケースがありますが、もし正しく作成されていた場合は効力があるものとみなされます。
逆に遺言書が作成されていない場合は、法定相続人を全員家に集めて遺産分割協議を行わなければなりません。
基礎控除以外に活用できる税金対策とは
基礎控除以外にも活用できる税金対策は多くあります。基本的に活用できるのが税額控除であり、適用される人とされない人がいるので注意が必要です。
それでは、基礎控除以外に活用できる税金対策についてご説明しましょう。
基礎控除以外に利用できる贈与税額控除
こちらは相続が開始される過去3年間に、被相続人からの贈与によって財産を取得して贈与税を支払った人が対象になる対策です。
過去3年間に被相続人から贈与という形で財産を取得すると贈与税を支払うことになります。
贈与税を支払っても財産自体は被相続人から相続した財産という扱いなので、同時に相続税も支払うことになるのです。
これでは二重課税となってしまうので、贈与税額控除の対象になる人は過去3年以内に支払った贈与税が控除されます。
基礎控除以外に利用できる配偶者の税額軽減
こちらは遺産を相続する際に必ず相続することが決まっている配偶者に対する税額控除です。これは遺産総額1億6000万円を超えない限り、いくら相続しても相続税は一切かかりません。
配偶者のみ税額が軽減されるため、目に見えて相続対策ができていることが実感できるでしょう。
基礎控除以外に利用できる未成年者の税額控除
こちらは相続が開始される現時点で年齢が20歳未満の未成年を対象にした税額控除です。相続人が20歳以下の未成年であれば、20歳になるまでの年数×10万円が控除されます。
つまり、相続開始時点で相続人が17歳なら、20歳になる3年間で合計30万円が相続税から控除されます。
基礎控除以外に利用できる障害者の税額控除
こちらは相続が開始した時点で85歳未満の障害者が対象になる税金対策の一つです。この税額控除は一般障害者と特別障害者によって控除される金額が違います。
一般障害者の場合は満85歳になるまでの年数×10万円が控除されますが、特別障害者の場合は1年につき20万円が控除されます。
つまり、一般障害者だと相続開始時点で60歳の場合、25年分の250万円が控除されるでしょう。同じく60歳の特別障害者の場合は25年分の500万円が控除されます。
基礎控除以外に利用できる相次相続控除
こちらは遺言書の内容に沿って財産を受け取った相続人のみが対象になっており、被相続人が過去1年以内に相続税を支払っている時に適用される税金対策です。
過去10年間で2度目以降の相続が発生した場合、最初に発生した相続税の一部を2回目に発生した相続税から控除できます。
基礎控除以外に利用できる外国税額控除
こちらは外国にある財産を相続した人を対象にした税金対策です。
外国にある財産を日本で相続した場合、外国で課税される税金と日本で発生する相続税の二重課税になってしまいます。
しかし、外国税額控除を利用すれば外国で支払った税金を日本で支払う相続税から控除できる仕組みになっています。
確定申告は必要?よくある注意点
遺産を相続した際に確定申告を行う必要性があるのか気になりますよね。しかし、結論から言えば
確定申告が必要なケースに該当する場合でない限り、確定申告を行う必要性はありません。
もしも遺産総額が基礎控除額を超えていた場合は相続税の申告が必要ですが、確定申告はどうなのでしょうか。
それでは、確定申告はどんな時に必要なのか、どんな注意点があるのかご説明しましょう。
確定申告が必要なケース
確定申告が必要なケースは、以下の通りです。
- 相続した土地や建物などを売却して所得を得た時
- 収入が発生する遺産を相続した時
- 相続した遺産を寄付した時
- 遺産を全て現金化して分割した時
土地や建物、有価証券といった遺産を相続して売却した場合、所得が発生するので確定申告を行わなければなりません。これは売却額から取得費を引き、税率をかけた金額が差し引かれます。
場合によっては遺産を譲渡した場合の取得費の特例が適用されるケースもあるので、チェックしておきましょう。
そして土地や投資物件などを相続した場合、収入が発生するので確定申告を行わなければなりません。
この場合、1月1日から相続が開始される日までに発生した収入は被相続人、相続が開始した日以降に発生した収入は相続人として確定申告を行います。
遺産を寄付する場合、必ずしも確定申告を行う必要性はありませんが、寄付金控除という節税ができるので確定申告を行った方が得になります。
ただし、寄付先の条件に当てはまる場合でしか利用できないので注意しましょう。
遺産を全て現金化することを換価分割と言いますが、全て現金化するということは新たな収入が発生した扱いになるので確定申告を行う必要性があります。
白色申告と青色申告の注意点
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、年間所得が300万円以下なら白色申告、300万円以上なら青色申告が適しています。
多くの人が青色申告を行うことになりますが、 被相続人が生前に確定申告を行っていた場合は白色か青色のどちらかを行ったことによって相続人が申告する時の提出期限が違います。
白色の場合、被相続人が死亡した年の1月16日以降に開業した場合は業務を開始してから2ヶ月が期限となり、それ以外で開業した場合は相続人が青色申告を行う年の3月15日までとなります。
青色の場合、1月1日~8月31日が命日なら命日から4ヶ月以内、9月1日~10月31日が命日なら同年12月31日まで、11月1日~12月31日が命日なら翌年の2月15日までが申告期限となります。
相続税の申告が必要な場合の手続き方法
もしも遺産総額が基礎控除額を超えた場合、相続税申告に必要な書類を全て用意して特例などを利用する際に必要な申告書や計算書、明細書を作成して故人の住所を管轄する税務署に提出するのが一般的な手続き方法の流れです。
相続税の申告書には第1表~第15表までありますが、適用させたい税額控除や特例があるところだけを選択して必要な書類を揃えるだけで構いません。
なお、申告に必要なのは被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と住民票除票、死亡診断書のコピー、相続人全員の戸籍謄本と住民票、印鑑証明、遺言書あるいは遺産分割協議書、相続人及び受遺者のマイナンバー確認資料と本人確認書類です。
まとめ
相続税には基礎控除があり、基礎控除額を超えない遺産総額なら相続税が発生することはありません。
しかし、遺産総額が基礎控除額を超えてしまった場合は相続税が発生するので申告しなければなりません。相続税に関する様々な税金対策があるので、相続税が発生しても落ち着いて対処しましょう。
税額控除や税金対策など、分からないことがあれば税理士に相談するのがおすすめですよ。法人事務所の税理士の中には無料で調査してくれることがあるので、費用の問題といった気になる問題も手軽に解決できます。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。
本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。













