国民皆保険の歴史
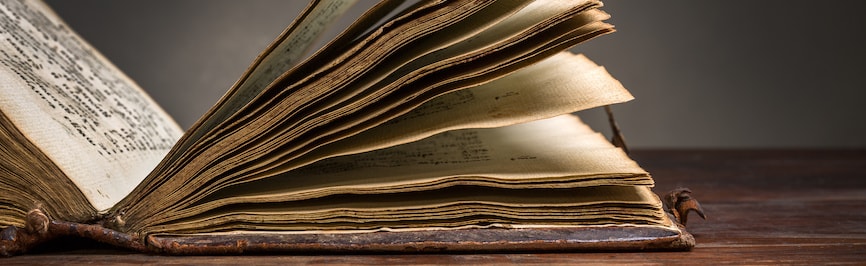
我々にとって当たり前の制度となっている国民皆保険制度。しかし、この国民皆保険制度は、戦争や高度経済成長など、さまざまな歴史的背景から先人達が苦労して築きあげた制度でもあるのです。
現在、医療財政は危機的状態となっており、国民皆保険制度の長い歴史上初めて存続が危ぶまれる声も出てきています。
長い歴史の中でもはじめて、その意義が大きく問い直されている国民皆保険制度。この記事ではその歴史を振り返り、これからのあり方を考えていきたいと思います。
目次
国民皆保険制度が始まる前の日本の医療
まず、国民皆保険制度が始まる前、日本の医療は歴史的にどのような状況にあったのか、その歴史を解説していきましょう。
医療保険制度が公布されたのが1922年。1927年にサービスが開始され、その歴史が始まりました。
当時の保険制度の被保険者は工場法及び鉱業法の適用を受けた企業で働く常用従業者を対象としており、多くの臨時雇用従業者は除外されていました。
保険料は事業主と従業者が負担、保険料は賃金の3%です。保険給付は、従業者の怪我や病気に対する療養、現物給付、労働ができない時期に対する手当金が中心となっていました。
なお、この給付の対象はあくまでも被保険者本人のみで、家族に対する給付はありません。
しかも、支給期間は180日以内に限定されていたので、当時歴史的に大流行していた結核にかかってしまった従業者など、長期にわたる療養者には、ほとんど効果がありませんでした。
さて、当時の医療保険の対象者数ですが、1934年に行われた制度改正までは、総就業人口約3000万人のうち、わずか200万人。対象者は一部大企業の従業者に限られていた、という歴史があるのです。
国民皆保険制度が始まった歴史的背景
では、国民皆保険制度はどのような歴史的背景をきっかけとして誕生したのかをみていきましょう。
1914年から1918年にかけて起こった歴史的大戦争、第一次世界大戦を受け、日本の工業は歴史的発展を遂げました。
しかし、それと並行して労働者の健康及び生活の安定を求める運動が各地で勃発するようになったのです。この運動がきっかけとなり、1922年に「健康保険法」がつくられました。
しかし、この保険法の対象は都市部で働く労働者のみに限定され、国民の数に対して加入者はそれほど多くはありませんでした。そんな折、1929年に歴史的大事件、世界大恐慌が起こります。
政府はこの歴史的大恐慌からの回復手段として新しい政策をとることにします。
それが功を奏して軍事関係の工業は大きな成長をとげましたが、農産物を扱う仕事はどんどん減少していきました。
当時の歴史を見ても、国民の半数は農家だったので、この政策のあおりを受けた農民たちが貧困と病気で苦しむ状態になってしまったのです。
しかしながら当時、日本は戦争のために、健康な国民を必要としていたので、軍事関係の工業がいくら発展しても、国民が病気で衰弱してしまうと元も子もありません。
このような歴史的背景があり、1938年に「国民健康保険法」が制定されました。
この保険法は農民が主な対象者でしたが、当時はまだ強制加入ではなく、任意保険だったのです。
その後1942年に法改正され、組合員の資格があるものは強制加入が適用されるようになりました。
その後も運営が組合から市町村へと変更されるなど、さまざまな歴史を経て、健康保険及び国民健康保険の加入者は徐々に拡大。1961年、ついに国民皆保険が達成という歴史的快挙を成し遂げます。
このように、国民皆保険は戦争という歴史とはきっても切り離せない…という歴史的背景があったのです。
国民皆保険制度と医療費の関係
さて、先ほどは国民皆保険制度の歴史を見てきました。ここからは少し歴史から離れて、国民皆保険制度の現状について解説していきましょう。
医療保険と医療費
現在の日本において我々は、病気や怪我をした場合、クリニックや病院などの医療機関及び調剤薬局で診察・治療・投薬などの医療サービスを受けることが可能です。
このサービスを受けた際にかかった費用が「医療費」です。我々は、国民皆保険制度によって、全ての人々が何らかの医療保険に加入しているため、病気や怪我をした際の医療費を全額自己負担する必要がありません。
我々が負担する医療費は、原則としてかかった医療費の3割となっています。
ただし、義務教育に就学する前の子供は2割、70歳以上75歳未満の被保険者は2割もしくは3割(所得に応じる)、75歳以上の後期高齢者医療保険制度の被保険者は1割もしくは3割(所得に応じる)となっています。
しかし、このように国民皆保険制度により、医療費を一部負担するのみで済んでいる、とはいえ、治療等の内容によっては負担する金額がかなり高額になってしまうケースも多々あります。
そこで、医療費の自己負担が過重になってしまわないように、医療保険には「医療費の自己負担分に対し、一定の上限を定めるという、「高額療養費制度」という制度が設けられています。
この制度は、医療機関及び薬局での自己負担額が、月単位で定められた一定額を超えると、その超えた金額を、医療保険より支給するものです。
ちなみに、自己負担額の上限額は、年齢や所得に応じて異なります。
さらに、同じ世帯内で同じ医療保険に加入している人に関しては、毎年8月1日~翌年7月31日の1年間にかかった医療保険及び介護保険の自己負担額の合計金額が一定金額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度が設けられています。
この制度のことを「医療・高額介護合算療養制度」と呼びます。
診療報酬制度とは
国民皆保険制度により、何らかの医療保険の加入者である被保険者が、患者として医療機関や薬局などで医療サービスを受けた際にかかった医療費は、医療機関にとっては、「自らが提供した医療サービスに対して支払われる対価」となります。
医療機関などでは、この対価を「診療報酬」という形で支払いを受けます。診療報酬の中には、技術やサービスの評価及び物の価格評価も含まれます。
この診療報酬は、医療保険の加入者である被保険者及び保険者より支払われる仕組みです。医療機関などでは、被保険者から医療費の一部を「患者負担額」として直接支払ってもらいます。
しかし、保険者からは、審査支払機関に対して診療報酬の請求を行ったうえで支払ってもらうようになるのです。
先ほども述べたように、診療報酬は医療機関が行った診療行為等のサービスの「対価」として支払われるものなので、保健医療の範囲や内容を定める「品目表」としての意味合いを持つと同時に、個々の診療行為の価格を決定する「価格表」の意味合いも持っています。
具体的にいうと、診療報酬は、医療機関が実施する診療行為ごとに、各々の項目に応じた点数が加算されていきます、1点の単価は10円として計算されます。
例えば肺がんで入院した場合
- 初診料
- 入院日数に応じた入院料
- 手術料
- 検査料
- 薬剤料
などが加算され、医療機関は、この合計額から患者の一部負担金を差し引いた額を、審査支払機関より受け取ります。
保険者は、審査支払機関が発行した審査済請求書に基づき、審査支払機関に対し、医療費の請求金額を支払う、という仕組みです。
ちなみに診療報酬は2年に1度、厚生労働大臣が厚生労働省に設置している「中央社会保険医療協議会」において、改定の必要性を審議したうえで諮問・答申を経て厚生労働大臣が定める決まりとなっています。
医療費の種類は?
医療費には、医科診療等にかかった診療費や薬局調剤医療費及び入院時の食事費、生活医療費、訪問介護医療費などがあります。
医療費は
- 医療保険による給付
- 後期高齢者医療制度及び公費負担医療制度による給付
- これらに伴い医療機関等を受信した人が自己負担で支払った医療費
の合計額のこと。
医療費を制度の区分別にわけると
- 健康保険組合・全国健康保険組合・国民健康保険、そして共済組合等その他の医療保険の適用者に対する給付としての「医療保険等給付分」
- 後期高齢者医療制度に対しての給付としての「医療保険等給付分」
- 生活保護法に関する医療扶助及び公害健康被害への補償等の給付としての「公費負担医療給付分」
- 患者が自己負担する「患者等負担分」
となります。
続いて、医療費を財源の負担別にわけると、
- 医療保険制度等の加入者である、被保険者及び事業主が負担しなければならない保険料
- 国庫負担金及び地方公共団体の負担金となる公費、
- 医療機関等にかかった患者の自己負担金
さらに、医療費を診療種類別にわけると
- 医科診療医療費
- 歯科診療医療費
- 薬局調剤医療費
- 入院時食事・生活医療費
- 訪問看護医療費
- 健康保険の給付対象になるはり師、柔道整復師等による治療・移送・舗装具等の費用
となります。
これからの国民皆保険制度のあり方
さて、続いては、国民皆保険の「これまで」の歴史ではなく、「これから」の歴史を考えていきたいと思います。
日本の医療保険は、さまざまな歴史を歩んだ末に「国民皆保険」という制度にたどりつきました。
そのおかげで現在、我々は長い歴史を振り返っても、最も手厚い医療を受けることができている、といえるでしょう。
しかし、この国民皆保険制度、実は歴史的危機に直面しているのです。
その理由が財政状況の悪化。国民皆保険が創設された1961年当時は、人口構成が若く、なおかつ政治も安定し、経済も成長過程にある、という歴史的背景がありました。
しかし現在は今までの歴史とは様子が異なっています。歴史上まれに見る少子化が進み、なおかつ経済も低成長時代。今の保険制度は、現役世代が高齢者を支えている、という状況になっています。
しかし、現役世代の人たちの中で、「我々の支払っている保険料の大部分が高齢者のために使われている」という状況に気づいている人はほとんどいません。
気付いていないがゆえに当事者意識が薄く、保険料未払いという事態が起こっている、と考えられます。
まずは、国民皆保険制度の仕組みを国民一人一人がしっかりと熟知する、ということが必要となるでしょう。
また、現在の国民皆保険制度においては、診療報酬は公的価格とされており、国が一律で厳格に管理しています。
しかしその一方で、医療サービスの供給については各医療機関に一任している、というのが現状です。価値観が多様化している今日では、医療サービスを受ける側の患者と、サービスを提供する医療従事者の間で、需要と供給のミスマッチが起こっている、といえます。
診療報酬の公的管理は必要なことではありますが、価格の決定が市場経済とあまりにかけ離れているため、消費者である患者のニーズに沿っていない、と考えられるでしょう。
例えば、多少高いお金を支払えば待ち時間が短縮できるなど、患者が医療サービスの価格や質に応じて、医療機関を選択できる環境を整えることができれば、国民皆保険制度を含めた医療機関への満足度は高まっていくのではないか、と考えられます。
引き続き、国民皆保険制度の歴史を維持し、歴史に見合ったさらなる発展を実現させるためには国民の合意の上で、医療保険制度の構造改革及び、医療提供体制の再構築が求められているのです。
国民皆保険と民間医療保険との違い
さて、ここまで国民皆保険の歴史や、そのあり方について詳しく解説してきました。ここで、皆さんの中には「国民皆保険で加入している健康保険と、民間の保険の違いってなんだろう?」と思っている方もいるかもしれません。
そこで、この項では、国民皆保険の歴史を理解したうえで、健康保険と民間医療保険の違いをわかりやすく解説していきましょう。
健康保険と民間医療保険の違い、表にすると以下のようになります。
| 健康保険 | 民間医療保険 | |
|---|---|---|
| 加入資格 | 全国民の義務 | 条件及び審査に基づく |
| 保険料 | 所得に応じる | 年齢・性別。保障内容に応じる |
| 給付 | 支払い窓口において、自己負担額が軽減される | 申請によって保険金を受け取る |
加入資格
健康保険は、国民皆保険制度によって全国民が加入することが義務付けられています。それに対して民間医療保険は、加入の際に審査があり、条件によっては加入できない可能性もあります。
保険料
健康保険の保険料は所得に応じて決定されます、それに対して民間医療保険は、被保険者の年齢・性別、健康状態及び保障内容により、保険料は異なります。
給付
健康保険は、病院等で医療サ―ビスを受けた際に保険証を提示すれば、原則としてかかった医療費の3割を負担すればよい、という仕組みです。
一方民間医療保険は、手術や入院等に対し、契約内容に応じた所定の金額が給付されます。
このように健康保険と民間医療保険は大きな違いがあります。
「基本の保障は健康保険で補い、健康保険でカバーできない部分を民間医療保険でおぎなう」というのが一般的な考え方である、と言えるでしょう。
まとめ:両方の保険を上手く活用して
今回は、皆さんなかなか知る機会のなかった国民皆保険制度の歴史について、詳しく解説してまいりました。
歴史的背景を知ることで、ますます保険が身近に感じられるようになったのではないでしょうか?
日本の「国民皆保険制度」は、長い保険の歴史の中でも、世界に誇ることができる優秀な保険制度です。
しかし、今までの歴史とは異なり、現代では国民皆保険制度によって加入している健康保険のみでは、十分な医療サービスを受けることができない可能性もあるのです。
そのときに頼りになるのが民間医療保険。健康保険ではカバーできない負担金を給付金で補ってくれます。
しかし、民間医療保険といっても種類はさまざま。適当に選んでしまうと、希望通りの保障を受けることができない場合もあります。
そこで頼りになるのが保険のプロフェッショナル。今の健康状態や年齢、ライフスタイルに適した医療保険を選択してくれます。
公的な健康保険の保障を理解しつつ、プロと相談しながら民間医療保険の検討を進めていくことがベストだといえるでしょう。
こうして上手く保険を活用していくことこそ、国民皆保険制度の歴史を守っていくことに繋がるのかもしれません。
[bengo]
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。
本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。













