税金の種類や使い道とは?税金対策・申告方法・控除の仕組みについて

さまざまな種類がある日本の税金。よく耳にする代表的な税金については知られていても、税金の使い道や仕組みについては、あまり知られていないことのほうが多いのが現実です。しかし、その税金について知識を深めておくと、税金対策ができ、負担を減らすことができます。税金について正しい知識を得て、賢く税金対策をしましょう。
目次
税金の種類と使い道とは?税金の仕組み
税金は、「直接税」と「間接税」の大きく二つの種類に分けることができます。税金を納める義務がある者と税金を負担する者が同じであるのが前者、異なっているのが後者です。
そして、国に納める税金のことを「国税」といい、地方自治体に納める税金のことを「地方税」といいます。税金は、「国税」の「直接税」または「間接税」、「地方税」の「直接税」または「間接税」に分けることができるのです。では、代表的な税金を中心に詳しくご紹介します。
国税の直接税(9種類)

- 所得税…個人の一年間の所得に対して課税されるもの
- 法人税…企業の所得に対して課税されるもの
- 相続税…亡くなった人から遺産を受け継ぐと課税されるもの
- 贈与税…財産を譲り受けると課税されるもの
国税の間接税(16種類)
- 消費税…商品の販売、サービスの提供などに課税されるもの
- 酒税…酒類を出荷する時、輸入する時に課税されるもの
- たばこ税…たばこを出荷する時、輸入する時に課税されるもの
- 関税…輸入する商品に課税されるもの
- 揮発油税…ガソリンを出荷する時、輸入する時に課税されるもの
- 航空機燃料税…航空機に積まれた燃料に課税されるもの
- 印紙税…一定額以上の取り引きの際、契約書などの文書作成に課税されるもの
地方税の直接税(9種類)

- 道府県民税(住民税)…個人と法人に、前年の所得に対して課税されるもの
- 自動車税…所有している自動車に課税されるもの
- 事業税…定められた事業を営んでいる個人と法人に、所得や収入に対して課税されるもの
地方税の間接税(4種類)
- 地方消費税…商品の販売、サービスの提供などに課税されるもの
- 道府県たばこ税…たばこの製造業者が、販売業者に売り渡すたばこに課税されるもの
- ゴルフ場利用税…ゴルフ場を利用した時に課税されるもの
税金の仕組み
日本国民の三大義務の一つである「納税の義務」。国民が国や地方自治体にお金を払うことで、国や地方自治体は、道路を作る、公共の施設を建てる、教育に使うことなどを行っているのです。
また、税金の金額の多くを占めるのは、所得税、法人税、道府県民税、事業税などの、個人や企業の稼ぎに対して課される税金です。そのため、稼いでいる人や稼いでいる企業ほど、多くの税金を納めるという仕組みになっています。
確定申告と年末調整の違いは?提出方法や時期・期間

「確定申告」と「年末調整」、それぞれよく耳にする言葉です。では、この二つはどのようなものなのでしょうか。まず、「確定申告」は、10種類ある所得について、自分で申告し、納税すること。「年末調整」は、会社が個人の一年間の給与を確定し、天引きしていた税金を年末の時期に計算しなおし、還付または徴収することです。
それぞれ税金対策に繋がる制度ですが、提出方法や時期などが違います。分かりやすく、「年末調整」からご紹介しましょう。
年末調整
私たちが会社から支給される給料からは、大まかな税額が毎月天引きされています。そのため、一年間の給料が確定する年末に、生命保険料の控除や住宅ローンの控除などを含めて、再度税金が計算しなおされます。そこで、税金を多く支払っていれば還付、支払いが足りなければ追加徴収をされるようになっているのです。
生命保険料の控除や住宅ローンの控除などというものは、それぞれの保険料を払っている人に対して、金額に応じて所得金額が差し引かれます。課税の対象となる所得が減少されることで、所得税や住民税の額が軽減されるという制度です。これらの保険料を払っている人は、年末調整の時期に申告をする必要があります。
確定申告
給与所得や事業所得、不動産所得など、10種類の所得から税額を計算する手続きを行うのが確定申告。会社員の場合は年末調整をしていれば、基本的には確定申告の手続きは必要ありません。しかし、年末調整をしていても、以下の場合は確定申告が必要となるので注意してください。
年末調整での控除の対象にならない場合
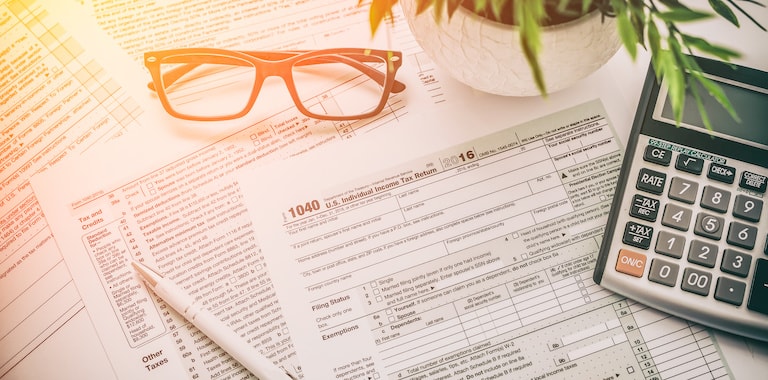
会社が行う年末調整では控除できないものがあります。それが、医療費、初年度の住宅ローン、ふるさと納税などの寄付金の控除、自然災害での損害や盗難による雑損控除、仕事に関わる支出による特定支出控除です。これらは確定申告の際に、自分で手続きをする必要があります。
年末調整で申告漏れがあった場合
生命保険料や2年目以降の住宅ローンを払っているのに、年末調整で申告をしていなかった場合は、自分で確定申告の手続きをすれば税金が還付されます。
年度途中に退社した場合
年度途中に退社後、新しく就職をしなかった場合、会社での年末調整の手続きがされません。よって、確定申告での手続きが必要となります。
確定申告の義務がある場合
年収2000万円以上の人は、年末調整をしてもらえないため、確定申告が必要です。また、副業をしていて、一ヶ所以上から給与所得がある人も確定申告の対象。年末調整は、一ヶ所からしかされないので注意しましょう。
確定申告の提出方法や時期・期間
確定申告の手続きは、自分が住んでいる地域の管轄の税務署で行うことができます。必要書類の提出方法は、直接持参、郵送、ネット上で手続きの3種類。分からない場合は、必要書類を直接税務署に持参すると、やり方を教えてもらえるでしょう。確定申告の時期や期間は、翌年の2月中旬頃から3月15日までです。
仮想通貨の税金の計算方法と確定申告の方法
仮想通貨は確定申告が必要

近年、認知度が高まってきている仮想通貨。紙幣や硬貨などの物質的な形がない、デジタル化された通貨です。インターネットを通じて円やドルなどの法定通貨で、交換、決済、融資、送金などができます。
そして、この仮想通貨を利用して、売却、商品の購入、他の仮想通貨との交換などで、一年間で利益が20万円以上発生した場合、副業での所得があるとみなされるため、確定申告の手続きが必要となるのです。
仮想通貨の計算方法
仮想通貨で儲けた利益は、「雑所得」として申告します。この「雑所得」は、毎月の給与所得と合算されて税率が計算されるのです。そのため、金額が増えるほど税率が上がってしまうというデメリットがあります。仮想通貨を利用する場合は注意が必要です。
仮想通貨の確定申告の方法
仮想通貨の確定申告には、申告書、会社から配布された源泉徴収票、仮想通貨の取引に関する書類(入出金明細書、取引履歴、ウォレットページを印刷したもの)が必要です。
税金対策の方法と仕組み-それぞれのメリット・デメリット

たくさんの種類の税金がある中で、支払う税金はできる限り少なくしたいと思う人がほとんどでしょう。では自分でできる税金対策には、どのような方法があるのでしょうか。おすすめの税金対策方法をご紹介します。
個人型確定拠出年金iDeCo
iDeCoとは、個人で行う確定拠出年金です。簡単にいうと、老後の資金を貯蓄しながら、税金対策もできるという制度。このiDeCoのメリットは、掛け金が所得控除の対象となることです。自分で負担した掛け金分、所得が下がるので、所得税や住民税の額も下がります。
また、iDeCoは運用時の利益に税金が掛からない、受け取る場合も税制が優遇されているというメリットも。デメリットとしては、60歳まで積み立てた資金の払い出しができないこと、途中解約も原則できないことです。iDeCo加入後、途中で取り崩したいと思ってもできないので注意しましょう。
また、iDeCo加入時に最低2,777円、運用期間中は月額167円が必要となります。長期間の投資であることを意識しておく必要があるでしょう。
ふるさと納税

好きな地方自治体に寄付金を贈ることで、お礼としてその自治体の特産品などがもらえるふるさと納税の制度。このふるさと納税のメリットは、寄付をした後、確定申告で手続きをすれば、2,000円を超えた金額が所得控除の対象となることです。
所得税や住民税の額が下がり、自己負担額は実質2,000円で地方自治体の特産品などがもらえるということになります。このふるさと納税のデメリットとしては、2017年に政府から自治体に自粛要請があったことから、もらえるお礼の品の還元率が下がっていること。
また、控除される額の上限が、収入や扶養の数などで決まりますが、内容が分かりにくいということです。上限額を超えてしまうと、控除の対象にならないため注意が必要でしょう。
両親を扶養に入れる
両親と同居をしていなくても、条件を満たしていれば扶養に入れることができます。すると、扶養控除の制度が受けられ、所得税や住民税の額が下がるというメリットが。税金対策をすることができるのでおすすめです。
両親を扶養に入れられる条件とは、両親の所得が合計38万円以下であることと、生活費などの送金や医療費の負担をしていて、生計を一緒にしていること。この税金対策のデメリットは、両親への送金額がある程度必要という点です。お小遣い程度の金額では認められないので注意しましょう。
医療費控除

医療費控除という制度を利用して税金対策を行うこともできます。これは1月1日~12月31日までの一年間で、支払いをした医療費が合計で10万円を超えた場合、確定申告で手続きをすることによって税金が戻ってくるという制度です。
この制度は、本人分の医療費だけではなく、生計を同じにしている親族の分まで合計して申告することができます。医療費控除の対象となるものには、一般診療代、医薬品代、市販の風邪薬、レーシック施術費用、歯の矯正やインプラントにかかった費用などです。
また、対象とならないものに、サプリメント代、コンタクトレンズ代、ホワイトニングにかかった費用、健康診断や人間ドックにかかった費用、通院にかかったガソリン代や駐車場代などがあるので注意してください。
特定支出控除
会社員で、条件に満たして入れば、特定支出控除という制度を利用して税金対策をすることができます。これは、仕事のためにかかった支出が多い場合に、所得控除ができる制度です。対象となる支出には、以下のものがあります。
- 通勤費(勤務先が全額負担をしている場合は対象外)
- 転居費
- 研究費や資格取得費
- 帰宅旅費(単身赴任の場合の旅費)
- 勤務必要経費(書籍代、スーツ代、接待代など)
ただしこの制度には、上記の対象となる支出が、給与所得控除額の1/2以上を超える場合という条件があるため、注意が必要です。この制度を利用するためには、まず給与所得控除額を把握しておきましょう。
保険料控除申告で税金が安くなる?制度と手続き方法

さまざまな税金対策の方法をご紹介しましたが、一番のおすすめは保険料控除申告。生命保険などの保険に加入し、申告を行うと、保険料として支払った一定額が、所得から差し引かれ、税金が軽減されるという制度です。対象となる保険は、死亡保険や学資保険などの「一般生命保険」、医療保険、がん保険、介護保険などの「介護医療保険」、個人年金制度税制適格特約というものが付加されている「個人年金保険料」です。
保険料控除申告の手続き方法
保険料控除申告は、会社員であれば年末調整で行います。自営業の場合は、確定申告での手続きが必要となるので、気を付けてください。
まずは、保険料控除証明書というものを集めましょう。対象となる保険に加入している場合は、各保険会社から10~11月ごろに送られてきます。原本が必要となるものなので、年末調整の時期まで大切に保管をしておいてください。そして、保険料控除申告書を記入します。保険会社の名前や保険の種類、契約者の名前、保険金の受取人、保険期間、一年間で支払った保険料の金額などの情報が必要です。
もし、契約者があなたではなく、妻などの保険に加入している場合でも、保険料を支払っている人があなたであれば、保険料控除の対象となります。申告漏れがないよう注意しましょう。年末調整で、保険料控除申告書と保険料控除証明書を一緒に提出すると手続きができます。
年末調整で申告漏れがあった場合、確定申告で手続きをすることが可能です。さらに還付の申請は、5年間をさかのぼって行うことができます。5年以内のもので手続きができていないものがある場合は申告しましょう。
知っているほど得をする税金の制度

税金について、税金対策について、知っていただけましたか?私たちは、知らず知らずのうちに多くの税金を支払っています。しかし、今回ご紹介した制度を知っていれば、税金対策をすることができるのです。これから税金対策をしたいという人は、まずは保険料控除から始めてみませんか?保険を充実させて、税金対策もできるおすすめの方法です。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。
本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。













