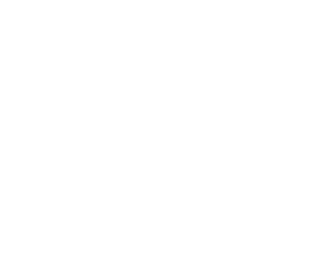収入がいくらあると確定申告をする必要がある?
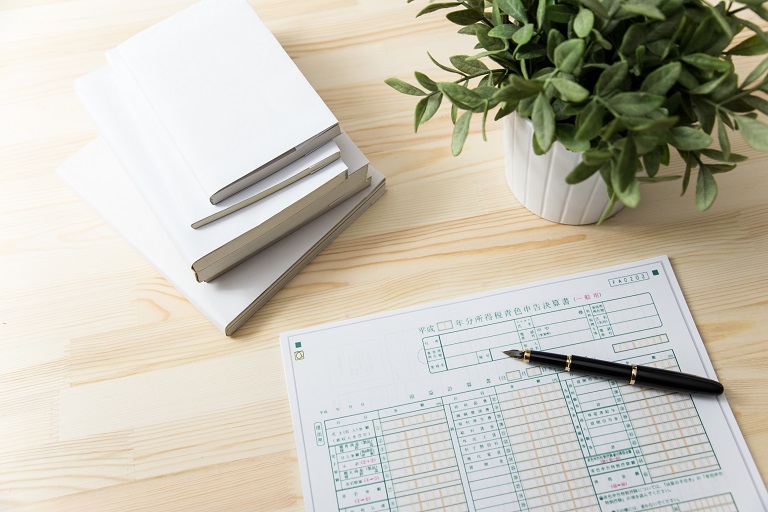
会社員として働いている場合、会社側で年末調整を行ってくれる場合がほとんどです。
そのため、確定申告とは縁がないと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、年収などの条件によっては、会社員であっても確定申告が必要になります。
ここでは、確定申告が必要になる年収の基準や、確定申告をしなくても良いけどした方がお得になるケースなどをご紹介しています。
確定申告書の書き方も紹介しているので、年収額やその他条件に該当する方は参考にしてみてくださいね。
![]()
確定申告は年収いくら以上が対象?
通常、サラリーマンの場合は会社側で年末調整を行ってくれるため、確定申告をする必要がありません。
しかし、一定額以上の年収がある方や、副業の収入などがある方は確定申告をしなければなりません。
また個人事業主やフリーランスとして働いている方は原則として確定申告が必要です。
まずは、サラリーマンと個人事業主それぞれについて、確定申告の対象となる年収や条件を見ていきましょう。
サラリーマンの場合
会社員として勤めている方の中で確定申告が必要になる年収や条件は以下の通りです。
- 年収が2,000万円以上ある
- 副業や投資で年収20万円以上を得ている
- 給与の受け取り先が2か所以上ある
年収が2,000万円以上ある
年収が2,000万円を超えている場合は年末調整の対象外となるため、確定申告が必須になります。
この際、年収額に通勤手当は含まれません。
1月1日から12月31日までの給与が2,000万円以上になった方は確定申告をしなければならないと覚えておきましょう。
また年収が2,000万円以上の場合は、配偶者特別控除や住宅ローン控除など一部の控除が受けられなくなるので注意。
生命保険料控除など適用できる控除の証明書と源泉徴収票をもとに、自分で確定申告を行うことになります。
副業や投資を行っている
副業や不動産、投資など本業ではない部分で年収20万円以上を得ている場合は別途確定申告が必要です。
年末調整で精算できるのは会社の給与のみなので、掛け持ちで働いているなど他のところから収入がある場合は申告しなければなりません。
確定申告を行わないと脱税とみなされる可能性があります。
その場合、追徴課税や重加算税を徴収され、本来よりも高い税金を納めることになってしまうのです。
日雇いのアルバイトやアフィリエイトの広告収入、不動産や株式の投資などで得た収益が該当します。
また保険の解約返戻金や報奨金などの一時所得についても、年間50万円を超える利益を得た場合は確定申告が必要となります。
給与の受け取り先が2か所以上ある
副業をしている場合と同様、本業以外の勤め先から年収20万円以上を得ている場合は確定申告の対象とみなされます。
年末調整ができるのは1か所のみと決められているので、年収20万円以上になる勤め先が複数ある方は確定申告が必要です。
個人事業主の場合
会社員ではなく、個人事業主として自ら起業したり、企業から業務委託を受けたりして働いている場合は、年末調整がないため確定申告が必要です。
ただし、個人事業主の場合は基礎控除として38万円の控除が受けられるので、年収が38万円を下回っている方は任意となります。
また開業した際に青色申告承認申請書を提出している方や、専従者登録を行っている方もいるでしょう。
青色申告承認申請書を提出している方は、複式簿記で帳簿付けを行うことで65万円の控除が受けられます。
専従者登録を行っている方は、同一生計内で支払った給与について控除が認められます。
これらの控除は確定申告を行うことが適用条件になるため、年収が少なくても確定申告を行うのがおすすめです。
その他
会社員や個人事業主以外に、一定額以上の年金を受け取っている方も確定申告が必要となります。
公的年金の受給金額から控除額を差し引いたうえで、収入が400万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。
確定申告をした方がお得になる人の年収や条件は?
上記の条件に当てはまる方は、確定申告が義務になるので忘れずに行うようにしましょう。
続いて、確定申告をしなくても問題ないものの、行った方がよりお得になるケースについてご紹介。
以下に該当する方は、節税のためにもぜひ確定申告を行ってみてくださいね。
副業で赤字が出ている
副業として行っている事業で赤字が出ている場合、確定申告することで赤字を翌年に繰り越すことができます。
年収20万円以下であれば確定申告は必須ではありませんが、税負担を抑えたいのであれば確定申告した方が良いでしょう。
また個人事業主として働いている方で、本業が赤字(年収38万円以下)の場合も同様。
特に前述した青色申告承認申請書を提出している方などは確定申告で大きな控除が受けられるのでおすすめです。
年度途中で退職した
年度途中で退職し、同年内に再就職をしていない場合は、会社での年末調整が受けられないため確定申告が必要です。
ただし、年のはじめで退職しており年収が20万円を下回っているような場合は必須ではありません。
それでも確定申告した方が各種控除や還付が受けられるので、やっておいて損はないでしょう。
年末調整を行っていない
年末調整の際に控除証明書を提出し忘れたり、紛失後の再発行が間に合わなかったりして控除が受けられなかった場合は確定申告をした方が良いです。
退職した場合と異なり、年末調整自体は受けられるため必須ではありませんが、控除できる金額があるなら確定申告した方がお得です。
この場合は年末調整をした会社の源泉徴収票が必要になるので、確定申告前に受け取れるようにしておきましょう。
年収103万円以下にもかかわらず所得税が差し引かれている
通常、年収が103万円以下の場合は全額控除されるため非課税です。
課税対象外にもかかわらず、毎月の給料から所得税を引かれている場合は確定申告によって還付が受けられます。
年末調整で受けられない控除を適用したい
控除の中には、確定申告でないと適用できない項目も存在します。
以下のような控除を適用したい場合は、年末調整を受けた方であっても確定申告をした方がより多くの還付金を受け取ることが可能です。
- 医療費控除
- 住宅ローン特別控除
- 寄附金控除
- 特定支出控除
医療費控除
医療費控除とは、年間で10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる控除です。(年収200万円以下の場合は所得の5%以上)
ケガや病気の治療費、出産に伴う入院費・分娩費、通院で利用した交通機関の費用などが該当します。
また医療費控除の金額に満たない場合でも、セルフメディケーション税制による控除を受けられる可能性があります。
セルフメディケーション税制では、「スイッチOTC」の対象薬を年間1万2,000円以上購入している方が対象となります。
医療費控除とセルフメディケーション税制を併用することはできないので、どちらか一方を選択しましょう。
住宅ローン特別控除
住宅ローン控除については、1年目のみ確定申告が必要です。
2年目以降は年末調整で精算を行うことができるようになります。
住宅ローン控除を受けるには以下の書類を準備する必要があります。
種類が多いうえそれぞれ発行場所が異なるので、漏れがないように注意しましょう。
- 住民票の写し
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 建物土地の登記事項証明書
- 建物土地の不動産売買契約書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
寄附金控除
ふるさと納税やNPO団体への寄附を行った方は確定申告で控除を受けることができます。
ふるさと納税をした場合で、ワンストップ特例制度を利用している方は確定申告をしなくても控除が受けられます。(他の控除を受ける場合は確定申告が必要)
ワンストップ特例制度を利用していない方、年間6か所以上にふるさと納税をした方は確定申告が必要です。
確定申告を行う際は、寄附金受領証明書の提出が必要となるので、失くさないよう注意しましょう。
特定支出控除
特定支出とは、勤務する上で必要な支出額が給与所得控除の半分を超える場合に適用できる控除です。
新調したスーツや、スキルアップのために取得した資格の受験費用などが対象となります。
こちらは勤務先で経費として認めてもらわなければならないので、適用したい場合は担当者へ相談してみてください。
手続き方法と期限を過ぎた場合の注意点
確定申告を行う期間は毎年2月16日から3月15日の間と定められています。
ここまで紹介した各ケースの中で、確定申告が必要になるケースに該当した方は上記期間内での確定申告が義務付けられます。
一方、確定申告をしなくても問題ないものの、行った方がお得になるというケースに該当した方は上記期間内でなくても構いません。
この場合は「還付申告」という扱いになり、確定申告の期間に関係なく過去5年間まで遡って申告することが可能。
確定申告の期間は税務署の窓口が混み合うため、避けた方が良いでしょう。
余裕のあるタイミングで必要書類を揃えて税務署へ提出してください。
確定申告の書類を提出する方法としては以下の3つがあります。
- 税務署の窓口へ直接提出する
- 税務署へ郵送する
- e-taxを利用する
都合の良い方法を選択して期限までに提出を行いましょう。
確定申告に必要なもの
確定申告を行うために必要なものは以下の通りです。
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 各種控除証明書
- 印鑑・通帳
確定申告書
確定申告書は国税庁のWEBサイトから印刷することができます。
会計ソフトやe-taxを利用する場合はあらかじめ用紙を用意しておく必要はありません。
源泉徴収票
年末調整を受けたうえで確定申告を行う場合は源泉徴収票が必要です。
年収2,000万円を超えており、年末調整を受けていない場合は不要。
途中で退職し再就職をしていない方は、退職時点までの源泉徴収票が必要となります。
各種控除証明書
医療費控除を受ける場合は医療費の明細書・領収書、寄付金控除を受ける場合は寄附金受領証明書のように、控除の対象であることを証明する書類が必要です。
紛失したものがある場合は速やかに再発行の連絡を行いましょう。
印鑑・通帳
還付金は振り込みという形で受け取るため、入金用の口座を明記する必要があります。
口座番号の書かれた通帳(またはカード)と認印(シャチハタは不可)をすぐ利用できるよう準備しておくと良いでしょう。
確定申告書の選び方
確定申告書には、「A様式」と「B様式」の2種類があります。
A様式の確定申告書は、給与所得や公的年金など項目が限られた簡単な内容になっています。
会社員やアルバイト・パートの方はA様式の確定申告書で進めるのがおすすめです。
B様式の確定申告書は、所得の制限がなく誰でも利用できます。
個人事業主の方や一定額以上の副収入を得ている方などはB様式を使うようにしましょう。
確定申告書の見方や書き方が分からない場合は、税理士や税務署の窓口へ相談してみましょう。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告の対象であるにもかかわらず、確定申告を行わなかった場合は脱税とみなされる可能性があります。
また3月15日を過ぎて確定申告を行ったという場合は期限後申告という扱いになります。
期限後申告の場合、「無申告加算税」と「延滞税」の2つの税金を追加で払わなければなりません。
無申告加算税
自主的に期限後申告を行った場合は所得税の5%、税務調査による通知後の場合は所得税の10%(所得税が50万円以上の場合は15%)が課せられます。
延滞税
2カ月以内に期限後申告を行った場合は所得税の年2.6%、2カ月を超えた場合は年14.6%が日割り計算で課せられます。
確定申告をすれば払い過ぎた税金を受け取ることができますが、期限を過ぎてしまうと逆に追加の税金を納めなくてはならなくなるのです。
確定申告は複雑で難しく感じるかもしれませんが、対象になっている年は必ず行うようにしましょう。
![]()
まとめ
- 会社員であっても年収2,000万円を超える場合は確定申告が必要
- 確定申告が必要ない方でも、確定申告によって還付を受けられる可能性がある
- 期限を過ぎたり無視したりするとペナルティがあるので注意
会社員・個人事業主・パートやアルバイトでは、それぞれ確定申告の対象となる年収や条件が異なります。
年収額や適用できる控除の種類を確認して、高い節税効果を発揮できるように準備していきましょう。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。
本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。