給付金の種類と受け取り条件について解説

一生のうちには出産や子育て、転職、入院など大きな出費が発生することや、逆に収入が制限されることなどがあります。そのような場面で頼りになるのが、給付金制度です。
給付金にはさまざまな種類があるため、いざというときのために、内容や受給条件などをきちんと把握しておくといいでしょう。ここでは、給付金の種類や保険金との違いなどについてご説明します。
目次
給付金制度とは-どこからもらえる?誰がもらえる?
給付金制度とは、定められた状況や条件に当てはまる場合に、金銭の支給を受けられる制度のことです。一般的に「給付金」と呼ばれるものには、大きく分けて次の2種類があります。
国や自治体からもらえる給付金

まず挙げられるのが、国や地方自治体などから支給される公的な給付金です。受給条件を満たしていれば、申請をすることで基本的に誰でも支給を受けられます。ただし中には、健康保険や雇用保険に加入していないと受けられないものもあるのが特徴です。また、種類によっては「給付金」と呼ばれず、「助成金」や「手当金」という名称が用いられるものも少なくありません。
国や地方自治体からもらえるものには、離職中に受け取れる「教育訓練給付金」や、子育て世代が受け取れる「児童手当」など、さまざまな種類があることが特徴です。一般に「給付金制度」という場合は、この国や地方自治体が定める給付金の制度のことを指すと考えましょう。
保険会社からもらえる給付金
次に挙げられるのが、任意で加入している民間の保険会社などから支給される給付金です。任意で生命保険に加入している人が、条件に該当する場合に申請をすることで受け取れます。
保険会社からもらえる給付金は、入院給付金や手術給付金など、病気になったりケガをしたりした場合に支給されます。上記の国や地方自治体による給付金制度とは、別ものであると考えましょう。
国や自治体からもらえる給付金・助成金と条件
それでは、国や地方自治体からもらえる給付金・助成金には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。受給の条件とあわせて主なものをご紹介します。
出産・育児に関する給付金・助成金と受給条件
妊婦健康診査助成金

妊娠中は、定期的に健診を受ける必要があります。この妊婦健診の費用の一部を助成するのが妊婦健康診査助成金です。受給するには、住民登録をしている地域で母子健康手帳と妊婦健康診査受診票の交付を受ける必要があります。
出産育児一時金
出産時にもらえる一時金で、1児につき最大42万円が支給されます。受給条件は、健康保険等に加入していること、妊娠4か月以上での出産であることなどです。
出産手当金
出産の前後で会社を休んだ場合に、その期間の給料の一部を支給するものです。出産前42日(多胎児の場合98日)から、出産翌日以降56日までの期間が対象で、標準報酬日額の2/3の金額が受け取れます。受給するには健康保険への加入が必要です。
児童手当
子どもが生まれてから中学校を卒業するまでの期間に受け取れる手当金です。0~3歳未満の場合15,000円、3歳~小学校終了まで10,000円(ただし第3子以降は15,000)、中学生は10,000円が受け取れます。ただし、所得制限を超える場合の支給額は一律5,000円です。受給するには、子どもの住所が日本国内にあることが条件となります。
子ども医療費助成制度
子どもが病気やケガなどで医療機関を受診した場合、医療費を地方自治体が助成する制度です。なお、助成の対象年齢や金額などは自治体によって異なります。受給するには、健康保険に加入していること、および居住地域に申請をして受給券の発行を受けることが必要です。
働くことに関する給付金・助成金
失業給付金

退職や倒産などにより仕事を失った場合に支給されるお金です。受給期間は原則として離職翌日から1年間で、離職前6ヵ月の賃金の50~80%の金額が受け取れます。受給条件は、離職日以前2年間に通算12ヵ月以上の被保険期間があることと、ハローワークで求職申込みをした上で、就職活動を行っていることなどです。
教育訓練給付金
自己の能力開発のために指定の講座を受講・修了した場合、受講費用の一部が給付されるもの。在職者の場合は雇用保険の被保険者、離職者の場合は被保険者であった人で、支給要件期間などの条件を満たす場合に受給することができます。
病気やケガに関する給付金・助成金
傷病手当金

病気やケガで会社を休んでいて報酬を受けられない場合に受け取れる手当金です。仕事を3日以上連続して休んだ場合、4日目以降の休業期間が支給の対象となります。支給期間は最長1年6ヵ月で、支給開始以前12ヵ月の標準報酬月額÷30×2/3が1日あたりの支給金額です。健康保険(ただし国民健康保険は除く)に加入していること、業務外の病気やケガの療養が目的であることなどが支給の条件になります。
高額療養費制度
医療機関や薬局で支払う医療費が高額になった場合に療養費の一部が支給される制度です。1ヵ月以内の医療費合計が、定められた上限額以上だった場合、上限を超えた分の額が支給されます。上限額は年齢や収入に応じて異なり、健康保険に加入していることが条件です。
住宅購入に関する給付金・助成金
住宅ローン控除(住宅ローン減税)

住宅ローンを組んで住宅購入をした場合に、毎年の所得税の一部が控除される制度です。年度末の住宅ローン残高、または住宅の取得価格のうち、少ないほうの金額の1%が控除されます。なお、減税される期間は最長で10年間(2019年10月~2020年末までの購入は13年間)です。
すまい給付金
住宅購入時に、助成金を受け取れる制度です。住宅ローン控除とは違って、ローン利用・現金取得のいずれの場合も給付を受けられます。2014年4月~2021年12月までに入居完了した住宅が対象で、消費税率8%の場合は最高30万円、10%の場合は最高50万円までを支給。住民票で住宅への居住が確認できること、収入が一定以下であることなどが条件です。
この他にも、身内に不幸があった場合に受け取れるものなど、法令で定められているものはいろいろとあります。国や自治体からもらえる給付金・助成金は、出産や失業、住宅購入など、一生のうちに起こりうるさまざまなケースに幅広く対応している点が特徴と言えるでしょう。
保険会社から受け取る保険金と給付金の違い
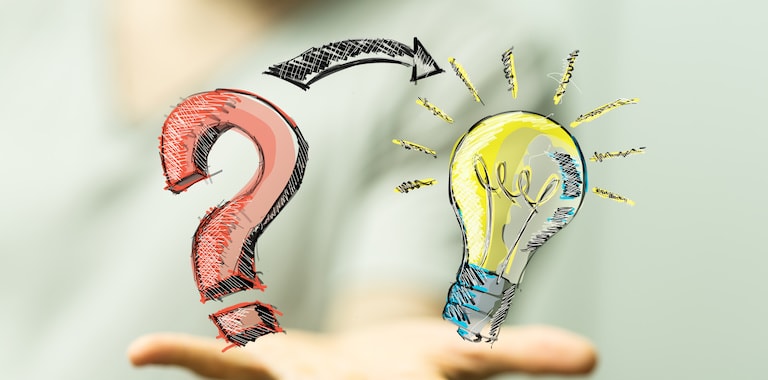
保険会社から支払われるお金には、主に「保険金」と「給付金」の2種類があります。保険会社からもらえる給付金について理解するために、まずはこの2つの違いについてご説明しましょう。
保険会社から受け取れる保険金とは
生命保険における保険金とは、生命保険の被保険者が亡くなった場合や、加入している保険が満期になったときなどに支払われるお金のことです。「死亡保険金」や「満期保険金」と呼ばれ、受け取ることができるのは基本的には1回のみ。受け取った時点で、その契約は終了となります。
保険会社から受け取れる給付金とは
生命保険における給付金とは、保険の契約期間中に所定の入院や手術などが発生した場合、保険会社から支払われるお金のことです。手術給付金や通院給付金などさまざまな種類があり、加入している保険の種類によって、どれを受けられるかは変わってきます。なお保険金とは違い、保険契約中であれば1回だけでなく複数回受け取ることもできる点が特徴です。
保険金・給付金の種類と加入の必要性
民間の保険会社から支払われる保険金や給付金には、どのような種類があるのでしょうか?主なものをいくつかご説明します。
保険会社から受け取れる保険金の種類
死亡保険金

保険の契約期間中に被保険者が亡くなった場合、主に遺された家族などに対して支払われるお金です。終身保険や養老保険など、さまざまな保険で受け取ることができます。
満期保険金
保険期間の満了時まで、被保険者が生存していた場合に受け取れるお金です。満期保険金の給付がある保険は「生存保険」と呼ばれ、主なものとして学資保険や養老保険などが挙げられます。
高度障害保険金
被保険者が病気やケガにより両目の視力や言語、そしゃく機能の喪失といった高度障害状態になったときに受け取れるお金です。高度障害保険金では死亡保険金と同額が支払われるため、この受け取りをもって保険契約は消滅となります。
リビングニーズ特約保険金
被保険者が「余命6カ月以内である」と判断されると、死亡保険金などの全額または一部を、前払いというかたちで受け取ることができます。死亡保険金の一部を生前に受け取ることで、死亡保険金を被保険者自身が活用できる点が特徴です。
保険会社から受け取れる給付金の種類
入院給付金

被保険者が病気やケガで所定の入院した場合に受け取れるお金です。入院日数に応じて規定の金額が支払われますが、契約内容によって対象となる入院限度日数が異なります。
手術給付金
被保険者が病気やケガで所定の手術を受けた場合に、受け取れるお金です。支給金額は一律の場合もあれば、手術の内容や入院日額に応じて決定される場合もあります。
通院給付金
通院治療をした場合に、日額で受け取れるお金です。主に退院後の指定期間が対象となります。
特定疾病に関する給付金
被保険者ががんや脳卒中、生活習慣病などの特定疾患を患って所定の状態になった場合に、受け取ることができるお金です。入院給付金に付加して支払われる場合と、病気の診断が下りた時点で支払われる場合等があります。
特定損傷給付金
不慮の事故により、被保険者が特定のケガを負った場合に受け取れるお金です。事故から指定の期間内にケガの治療を受けた場合に支給されます。対象となるケガとして挙げられるのは、所定の骨折や関節脱臼、腱の断裂、永久歯の喪失などです。
先進医療給付金

被保険者が、厚生労働大臣の定める「先進医療」に当たる治療を受けた場合、受け取ることができるお金です。保障内容によって、技術料の実費が支払われる場合と、治療内容によって規定の金額が支払われる場合があります。
女性疾病入院給付金
被保険者が乳がんや子宮内膜症など女性特有の疾患により所定の入院をした場合、受け取ることができるお金です。一般的には、入院給付金に上乗せして支給されます。
ここで挙げているものは、保険会社から支払われる保険金や給付金の種類の一部です。国や自治体による給付金は、生活全般に幅広く対応している点が特徴。それに対して保険会社による保険金や給付金は、自分の体に万が一のことがあったときなどに、より手厚いサポートを受けられることが特徴です。
病気やケガなどによる出費を公的な給付金だけで補えない場合でも、安心して生活を送れるようにするための助けとなるのが、任意保険への加入であると言えるでしょう。
保険の給付金には税金はかかる?
死亡保険金や満期保険金などを受け取る場合は、金額によっては税金がかかることもあります。しかし保険の給付金を受け取る場合、一部例外を除いて税金はかかりません。所得税法施行令第30条の中では、生命保険契約に基づく給付金のうち、心身の傷害に基因するものは非課税となることが定められています。ここで、非課税になるものと、課税対象になる可能性のあるものを見てみましょう。
保険会社による給付金で非課税のもの

基本的に、病気やケガを治療する上で生じた費用を補填するものは、税金がかからないと考えましょう。非課税の給付金としては、主に次のようなものが挙げられます。
- 入院給付金
- 通院給付金
- 手術給付金
- 介護一時金
- 特定疾病z関する給付金
- 先進医療特約の給付金など
なお、保険金の中でもリビングニーズ特約保険金や高度障害保険金などは、これらと同様で非課税となります。
保険会社による給付金で課税対象となるもの
一方、次のようなケースでは、受け取った給付金が課税の対象となる場合があります。
祝金や生存給付金を受け取った場合
祝金や生存給付金は満期保険金の前払いと見なされるため、満期保険金などと同様「一時所得」として税金が課せられます。ただし1年間で受け取った金額が50万円以下である場合、または保険料の支払い総額が受け取った金額より大きい場合、税金はかかりません。
給付金を相続する場合
受け取った時点では非課税であっても、そのまま受取人が亡くなって相続財産となって遺族に引き継がれる場合は、相続税が発生することがあります。
給付金の知識を深め万が一への対策を
国や地方自治体からもらえる公的な給付金と、民間の保険会社からもらえる給付金には、さまざまな種類があります。万が一のときに金銭のことで慌てないためにも、「どのような場合に、どこからお金が出るのか」をきちんと把握しておきましょう。
まずは公的な給付金制度について知識を深めた上で、不十分だと思われるところは任意保険でカバーし、もしものときの備えをしっかりしておくことが大切です。自分にとって必要な保険とそうでないものがよく分からない場合は、プロに相談してみるといいでしょう。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。
本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。













