学資保険は生命保険料控除の対象!申請方法を解説
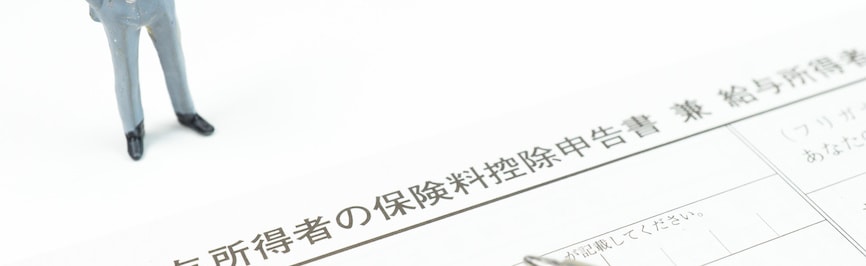
「学資保険は年末調整で控除の対象になる」。学資保険に加入をした際、保険会社からこのように言われた方も多いのではないでしょうか?
確かに学資保険は年末調整の控除の対象になり、支払った保険料に応じて控除される金額が異なります。しかし、控除の申請をする際には、年末調整で配られる書類の書き方と、控除の対象となる保険料の金額に注意をしなければいけません。
そこで今回は、学資保険の年末調整の書類の書き方と、細かな注意点を解説していきます。
学資保険の控除申請の方法に入る前に、まずは「年末調整とは何か?」という基本的な点から解説していくので、保険料の控除申請について全く分からない人も参考にしていただけるかと思います。
目次
年末調整の仕組みと書き方
年末調整とは、会社と雇用契約を結び給与を受け取っている人を対象とした納税手続きを指します。毎月の給与から天引きされている所得税について、年末に改めて課税対象額をまとめて清算します。
年末になると、その年に支払う必要がある所得税額が決まるので、給与から天引きされていた所得税が多すぎた場合には還付金が戻り、所得税が足りなければその分の金額を増やして給与から天引きされることになります。
このように、年末調整は会社員が正しく所得税を納めるための仕組みと言えますが、もう一つ重要な役割があります。それは、納税時の生命保険料控除を行うこと。
みなさんも、年末調整の際に覚えがあるかと思いますが、もし生命保険に加入している場合には、加入している保険について申告が必要です。そして、所定の書類を提出することで、所得税・住民税の一部を減らす税額控除を受けることができるのです。
この税額控除は、各家族の事情を考慮して、生命保険料を所得税・住民税の控除の対象として税負担を抑えるために導入されています。
控除の申請をするには、自分自身で「給与所得者の保険料控除申告書」の書類に記入・提出が必要です。
給与所得者の保険料控除申告書の書き方
年末調整で記入が必要になる「給与所得者の保険料控除申告書」の書き方は、いたって簡単です。
自分が加入している保険の種類や保険会社の名前、保険の契約期間、自分が支払った保険料を、該当する欄に書いていけば良いだけ。「自分が加入している保険の詳細な内容なんて覚えていない」という方は、保険加入時にもらう「保険証券」を確認しましょう。
「1年間に支払った保険料の総額が分からない」という方も、問題ありません。毎年10月~11月頃に、その年に支払った保険料が記載された「控除証明書」という書類が保険会社から送られてきます。そこに記載されている内容を、そのまま書き写せば良いのです。
ただし、「給与所得者の保険料控除申告書」の記入時には2点注意点があります。
1つ目は、控除の申請をしたい生命保険料について、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類に分けて申請をする必要があること。
3種類とも、1枚の書類の中で一緒に控除の申請が可能ですが、自分が加入している保険が3種類のうちどれにあたるのかを把握しておく必要があります。
2つ目は、年金保険で生命保険料控除の対象となるのは、支払った保険料の全額ではなく、一部のみであること。そして、「給与所得者の保険料控除申告書」の記入時には、控除の対象となる金額を自分で計算して記入する必要があります。
計算式自体は非常に簡単で、「給与所得者の保険料控除申告書」にも計算方法は載っています。そのため、特に心配することはありません。
さて、まずは年末調整について基本的な内容を説明してきました。
ここからは、本題である「学資保険についての保険料控除申請をする」という点に着目し、先ほどの2点の注意点を絡めながら解説していきます。
学資保険は年末調整の対象になる?
先ほど、注意点として、控除の申請をしたい生命保険料を「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類に分けて申請をする必要があることを挙げました。
生命保険料控除として年末調整で申請することができる保険は、保険商品によって下記の表の通り3種類に分けられます。
年末調整で申告できる生命保険料控除の種類
- 一般の生命保険料控除
個人年金保険(税制適格特約なし)、終身生命保険、定期生命保険、収入保障保険、学資保険など - 個人年金保険料控除
個人年金保険(税制適格特約あり) - 介護医療保険料控除
医療保険、がん保険、介護保険など
学資保険は、生命保険料控除の中でも、「一般の生命保険料控除」に含まれます。
そもそも学資保険は、貯蓄目的が強く「生命保険」という印象が薄いという方も多いでしょう。しかし、学資保険は契約者が死亡・高度障害の際に保険料の払い込みが免除になるなど、生命保険の要素が一部入っています。
このような背景から、学資保険も年末調整の生命保険料控除対象であり、その中でも「一般の生命保険料控除」に分類されるのです。
そのため、学資保険に加入をしている方は、年末調整で控除の申請をする際に「一般の生命保険料控除」の欄に必要事項を記入するようにしましょう。
万が一、自分が加入している保険が3種類のうちどれに該当するのかわからなくなってしまった場合には、保険会社から毎年送られてくる控除証明書に明記されているため、そちらを参照しましょう。
学資保険の生命保険料控除の金額はいくら

次に、学資保険の生命保険料控除の対象額はいくらなのかを見ていきましょう。
2つ目の注意点でも挙げましたが、年末調整で生命保険料控除の対象となるのは、支払った保険料の全額ではなく、一部のみです。
控除の対象となる金額は、その年に支払った保険料額と、自分が加入している保険が新制度化、旧制度かによって異なります。
この新制度・旧制度は、2012年に行われた生命保険料控除制度の改正を区切りとして分けられています。2011年12月31日以前(旧制度)に契約・更新をした保険は旧制度、2012年1月1日以降(新制度)に契約・更新をした保険は新制度とされ、控除額の計算方法や上限額が異なるのです。
控除の対象となる金額の計算方法は、下記の表の通りです。
新制度の計算方法(2012年1月1日以降に契約・更新した学資保険)
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超~80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
旧制度の計算方法(2011年12月31日以前に契約・更新した学資保険)
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 25,000円超~50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
| 50,000円超~100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
ここで注意が必要なのは、年末調整で学資保険の保険料控除をする場合、同時に加入している生命保険や医療保険の保険料も足した上で控除の対象額を算出しなければいけないという点。
保険料控除は、あくまで「一般の生命保険料控除」という分類に対して適用となるため、
終身生命保険、定期生命保険、収入保障保険、学資保険などを全部足した保険料が対象となります。
以上の点に注意して、年末調整で生命保険料控除の対象となる金額を算出の上、「給与所得者の保険料控除申告書」に記載していきましょう。
なお、年末調整の書類に記入する必要ありませんが、学資保険などの生命保険料控除を行うことで、所得税だけでなく住民税も控除されます。
住民税の控除額については、下記の表のとおりです。
新制度の計算方法(2012年1月1日以降に契約・更新した学資保険)
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 12,000円超~32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
| 32,000円超~56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
旧制度の計算方法(2011年12月31日以前に契約・更新した学資保険)
住民税
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 15,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
| 40,000円超~70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000円 |
住民税は年末調整での申請は必要ありませんが、保険料の控除申請で所得税だけでなく住民税も減額されることは知っておいて損はないでしょう。
妻名義の学資保険も対象かどうか
学資保険の生命保険料控除を申請する際に、多くの方が疑問に思うのが「妻名義の学資保険も、夫である自分が控除の申請をしても良いのか」という点です。
名義は妻で、保険料の支払いも妻である場合には、当然夫の控除対象にはなりません。しかし、名義は妻ですが、保険料を支払っているのは夫という場合には、どうなのでしょうか?
答えとしては、「夫の年末調整で控除申請の対象となる」です。
ただし、その際には妻と夫の関係が下記の条件を満たしている必要があります。
- 戸籍上の配偶者であること
- 生計を一つにしていること
- 妻の年収が103万円以下であること
この3つの条件を満たしていれば、妻名義の学資保険でも、年末調整によって夫の所得に生命保険料控除が適用されます。
個人事業主などは確定申告で控除が可能

ここまでは、企業に勤める方向けに会社の年末調整で生命保険料控除をする方法を説明してきましたが、個人事業主などの場合は確定申告で控除が可能です。
確定申告で学資保険の控除を申請する場合も、やらなければいけないことは年末調整と変わりません。「一般の生命保険料控除」という分類で他の生命保険や医療保険と合算した際の控除対象金額を算出し、記入するだけです。
確定申告は、毎年おおむね2/16~3/15です。この期間の間に確定申告をしなければ、控除は適用されないので、忘れずに行うようにしましょう。
また、個人事業主に限らず、会社の年末調整で学資保険の控除申請を忘れてしまった人も、確定申告で控除の申請をすることが可能です。手間は増えてしまいますが、忘れてそのまま課税されるよりも、控除で税額を減らした方がメリットがあります。せっかくの税額控除なのですから、忘れずに活用することがおすすめです。
学資保険の年末調整は簡単にできる
今回は、学資保険の年末調整における税額控除の申請方法を解説してきましたが、いかがでしたか?
控除の対象金額の計算など、少し面倒なところはあるものの、保険会社から送られてくる控除証明書をそのまま写せば良いだけなので、意外と簡単に申請することができます。ぜひ、毎年の年末調整で控除の申請をしてみて下さい。
会社の年末調整の機会を逃すと、確定申告でわざわざ自分で控除の申請をしに行かなければいけなくなってしまいます。無駄な手間を後からかけるよりも、一番楽な年末調整で忘れずに行うようにしましょう。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。
本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。













