安い学資保険を選ぶ際の注意点とは
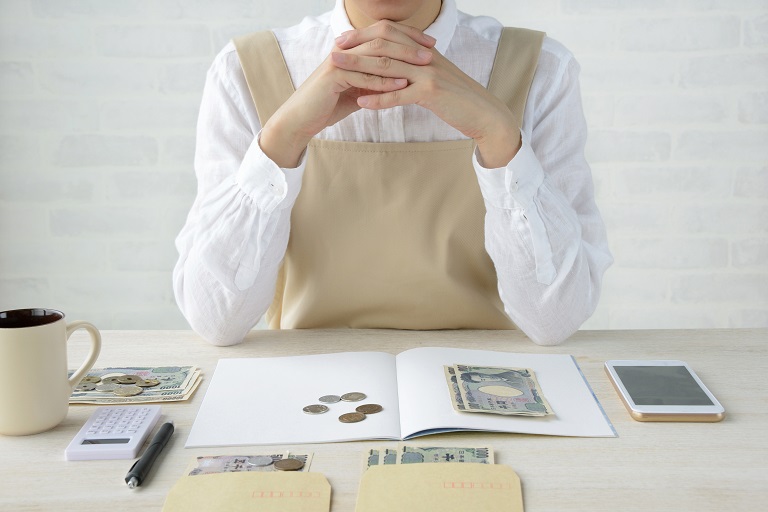
子どもの教育に必要な資金を貯めるひとつの方法として、多くの人に利用されている学資保険。
学資保険は生命保険の一種でもあるため、貯蓄性だけでなく将来のための保障も付帯できる特徴があります。



この記事は、次のような人におすすめの内容です。
この記事は5分程度で読めます。
保険料が安い学資保険に加入しても問題はないのか、根本的な疑問から解決していきます。
目次
安い学資保険は本当にお得?人気商品は安い?


保険料が安い学資保険の2パターン
学資保険で保険料が安くなっている商品には、主に以下の特徴を持っているものが多いです。
- 保障内容がシンプル
- 返戻率が低い、払い込んだ保険料よりも受け取れる学資金が少ない
どちらも、知らずに契約してしまうと大きなデメリットとなりますので、ひとつずつ解説していきます。
保障内容がシンプル
学資保険には、教育資金を準備するための「貯蓄」機能と、万が一の備えとしての「保障」機能とがあります。

安い学資保険の中には高い返戻率をうたっている商品もあり、その場合は保障機能をシンプルにして保険料の大部分を運用に回す必要があります。
しかし、保障機能を最小限にすると万が一の際の保障が不十分になってしまい、たとえば子どもが病気やけがで入院した場合や、親の死亡というリスクなどに十分に対応できない可能性があります。

返戻率が低い、払い込んだ保険料よりも受け取れる学資金が少ない
安い学資保険は高い返戻率をうたっているものがある一方、手厚い保障を重視している商品もあります。

安い保険料の大部分を保障機能に重点的に利用することで、払い込んだ保険料よりも受け取る満期保険の方が少額となる「元本割れ」を起こしてしまうことがあります。
学資保険は貯蓄と保障のふたつの機能があるとはいえ、払い込んだ保険料よりも受け取る金額の方が少ないのは「貯蓄」という面からみると不十分です。
また、元本割れまではしなくても、返戻率がほとんどない場合も、長期間保険料を納め続けているメリットを感じにくいですよね。

安い学資保険がお得とは限らない
これまでご紹介してきた内容で、保険料が安い学資保険は保障内容や返戻率に注意しなくてはならないことがわかりましたが、実はもうひとつ気をつけなければならないことがあります。
学資保険は満期日と満期保険金が同じであっても、加入した年齢や払込期間などによって毎月支払う保険料が異なるため、単純に保険料だけを比較して「これはお得!」とはいえないということです。
たとえば、保険料の払い込みを子どもが18歳になるまでに設定し、18歳で300万円の満期保険金が受け取れるという契約内容の場合で考えてみましょう。
子どもが0歳のときから保険料を払う場合の払込年数は18年間ありますが、5歳から支払う場合は13年間しかありません。そのため、1年間に支払う保険料は当然0歳から支払う方が安くなります。

学資保険の保険料を安くする5つのポイント
安い保険料で必要な学資金を貯めるためのポイントは、次の5つです。
- 他の保険商品と組み合わせる
- 保険料をまとめて支払う
- できるだけ年齢が若いうちに加入する
- 付帯する保障を限定する
- インターネットから契約する
これらについて、1つずつ詳しく見てまいりましょう。
1. 他の保険商品と組み合わせる
生命保険や損害保険など、すでに加入している他の保険と同じ会社で学資保険を契約すると割引が適用される場合があり、保険料が安い状態で契約できることがあります。


すでに契約している保険商品がなくても、学資保険に加入するタイミングで同時契約をすると保険料が安い状態で加入できるケースもあります。
学資保険によっては兄弟割引制度がある場合もあるので、保険料が安い状態で学資保険を契約できる可能性があります。
2. 保険料をまとめて支払う
学資保険は、総払込保険料が高額になるため保険料を毎月払うのが一般的ですが、一時払いや年払いなども選択できます。

月払い等に比較して安い保険料で将来のための学資金が貯められ、返戻率が高くなるので経済的にお得と言えるでしょう。
3. できるだけ年齢が若いうちに加入する
学資保険に加入するときの親子の年齢が若い方が、支払う保険料の金額は安く設定されています。
安い学資保険に加入するか迷っている人は、できるだけ早く決断することをおすすめします。
4. 付帯する保障を限定する
学資保険は生命保険のひとつなので、将来のリスクに幅広く備えるために死亡保障や医療保障などさまざまな保障を付帯できます。
あれこれ付帯すると保険料は安い状態を保てません。
また将来のリスクに備えられる保障が付けられるのは、学資保険だけではありません。

保障内容の重複を避けると、保険料は安い状態を保てる可能性があります。
5. インターネットから加入する
学資保険を取り扱う保険会社によっては、店舗からでなくインターネットから加入すると安い保険料が適用されるキャンペーンを実施していることがあります。
経済的なことを考えて、インターネット申し込みで安い保険料になる学資保険を探すのもいいでしょう。
保険料が安くて返戻率が高い学資保険はある?
学資保険への加入を検討している方にとって、最も理想的な学資保険は「保険料が安く返戻率の高いもの」でしょう。

というのも、学資保険で支払う保険料は、将来お祝い金や満期保険金などで支払うときのために、保険会社で運用して資金を大きくしていますが、ここ近年の低金利の影響もあり、以前のように高い返戻率を出すことが難しくなっています。

しかし、前章でご紹介したように、ご自身で対策をとることで返戻率を上げることはできますので、「返戻率を上げる対策を取れる学資保険を選ぶ」ことがポイントになります。
保険料をまとめて支払える学資保険を選ぶ
学資保険の払込方法には、以下の4つの方法が挙げられます。
学資保険の払込方法
- 月払い
- 半年払い
- 年払い
- 前期前納払い
- 一時払い
まとめて支払うほど保険料総額が安くなるため、結果として返戻率を上げることにつながります。
前期前納払いや一時払いで支払えると、運用に回せる期間が長くなるため、より返戻率が上がる可能性が高くなります。


仮に保険料が毎月1万円だとすると、定額積立預金も毎月1万円ずつになります。すると、丸一年経過したときには定額積立預金で12万円が貯金できているはずなので、それを学資保険の年払いに充てるのです。学資保険にもよりますが、年払いにすると11か月分の保険料程度で済むことが多いので、1万円程度安くすることができます。
そして、また毎月1万円ずつ積立貯金預金を始めて翌年も年払いで支払うと、ずっと月払いで支払うよりも保険料を安くでき、返戻率を上げることにつながります。
短期払いができる学資保険を選ぶ
学資保険の保険料の払込期間を短くすることで、保険料を安く抑えることができ、返戻率を高くできる可能性があります。
たとえば、保険料を子どもが18歳になるまで支払い続けるのではなく、10歳や12歳といった早い段階で納めてしまうことで、1回の保険料は高額になりますが、支払総額を安くすることができ、返戻率を上げることにもつながります。

返戻率にとらわれず家計とのバランスを大事にする
返戻率を上げるためのふたつの対策をご紹介しましたが、学資保険の返戻率を上げることだけを考えて高額な保険料を短期間で支払おうとすると、家計に大きな負担がかかってしまうことがあります。

教育費にいくらかかるか把握しておこう
学資保険に加入する際には、子どもの教育費にいくらかかるのかも把握しておく必要があります。
進学に費用なお金を準備しておくために「いつまでにいくら必要なのか」を知っておくと、計画的に貯蓄していくことができます。
では、幼稚園から大学まで実際に教育資金がいくらかかるのか、目安を確認していきましょう。
幼稚園に必要な費用
幼稚園などに3年間通わせた場合の平均費用は、公立と私立それぞれ以下の通りです。
| 費目 | 公立 | 私立 |
| 学校教育費 | 61,156円 | 134,835円 |
| 学校給食費 | 13,415円 | 29,917円 |
| 学校外活動費 | 90,555円 | 29,917円 |
| 1年間合計額 | 165,126円 | 308,909円 |
| 3年間合計額 | 495,378円 | 926,727円 |
2019年10月より幼児教育・保育の無償化が始まったため、制度前よりも教育費が大幅に減額されています。
小学校に必要な費用
では次に小学校に必要な費用について見ていきましょう。
| 費目 | 公立 | 私立 |
| 学校教育費 | 65,974円 | 961,013円 |
| 学校給食費 | 39,010円 | 45,139円 |
| 学校外活動費 | 247,582円 | 660,797円 |
| 1年間合計額 | 352,566円 | 1,666,949円 |
| 6年間合計額 | 2,115,396円 | 10,001,694円 |
公立でも6年間通うと約210万円が必要で、私立になると約1,000万円もの費用がかかることがわかります。
公立では「学校外活動費」が、私立では「学校教育費」が最も大きな割合を占めています。
中学校に必要な費用
では次に中学校に必要な費用について見ていきましょう。
| 費目 | 公立 | 私立 |
| 学校教育費 | 132,349円 | 1,061,350円 |
| 学校給食費 | 37,670円 | 7,227円 |
| 学校外活動費 | 368,780円 | 367,776円 |
| 1年間合計額 | 538,799円 | 1,436,353円 |
| 3年間合計額 | 1,616,397円 | 4,309,059円 |
中学校になっても、公立は「学校外活動費」が、私立は「学校教育費」が最も高額となっています。

高校に必要な費用
高校で必要な費用は以下の通りです。
| 費目 | 公立 | 私立 |
| 学校教育費 | 309,261円 | 750,362円 |
| 学校給食費 | -円 | -円 |
| 学校外活動費 | 203,710円 | 304,082円 |
| 1年間合計額 | 512,971円 | 1,054,444円 |
| 3年間合計額 | 1,538,913円 | 3,163,332円 |
高校になると給食がなくなるため、その分の費用はかからなくなります。
また、2020年の4月から私立高校の授業料無償化がスタートしたことで、以前よりも費用がかからなくなっています。
高校まで公立で550万円、私立なら約1,800万円かかる
ここまでの金額をまとめてみると、小学校から高校までにかかるお金の目安は以下のように計算できます。
| 公立 | 私立 | |
| 幼稚園(3年間) | 495,378円 | 926,727円 |
| 小学校 | 2,115,396円 | 10,001,694円 |
| 中学校 | 1,616,397円 | 4,309,059円 |
| 高校 | 1,538,913円 | 3,163,332円 |
| 合計 | 5,766,084円 | 18,400,812円 |
幼稚園から高校まですべて公立の場合でも580万円程度の教育資金が必要になり、すべて私立の場合は1,800万円程もかかってしまうことがわかります。
大学に必要な費用
大学進学に係る費用は一概にはいえず、まず公立か私立かで異なるうえ、学部によっても大きく異なります。
具体的な費用の目安は以下の通りです。
| 大学・学部 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 4年間合計 (医学部・歯学部は6年間) |
| 国立大学 | 28万2,000円 | 53万5,800円 | - | 242万5,200円 |
| 国立医・歯学部 | 28万2,000円 | 53万5,800円 | - | 349万6,800円 |
| 私立文系 | 22万5,651円 | 81万5,069円 | 14万8,272円 | 407万9,015円 |
| 私立理系 | 25万1,029円 | 113万6,074円 | 17万9,159円 | 551万1,961円 |
| 私立医歯系 | 107万6,278円 | 288万2,894円 | 93万1,367円 | 2,396万1,844円 |
【参考】:
〇文部科学省「国立大学と私立大学の授業料等の推移」
〇文部科学省「令和3年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について
国立大学の医・歯学部では約350万円、医・歯学部以外の学部では、約250万円かかることになります。
私立大学では、文系で約400万円、理系で約550万円、医歯系で約2,400万円の費用がかかることがわかります。
保険のプロに適切な保険料・保険金額を試算してもらおう


結論から言えば、安い学資保険に加入しても大丈夫なのかと心配するのではなく、きちんと保険のプロに相談することをおすすめします。

子どもの教育費を貯蓄だけで賄うのは経済的にも負担が大きいので、できるだけ安いお金で賢く学費を貯められる方法をプロに見極めてもらえば安心です。
まとめ
今回は、保険料の安い学資保険が本当にお得なのか、契約時の注意点や保険料を抑えるコツについて詳しく解説しました。
保険料が安い学資保険は、最低限の保障内容で返戻率が低い傾向にあります。そのため、保険料が安いからといって必ずしもお得だとは言い切れません。
安さだけでなく、必要な保障を十分に受けられるのか、保険料とのバランスを考えながら検討することが大切です。
お金に関する知識がなければ、家計に合った教育資金の準備方法を判断するのは難しいかもしれません。教育資金の準備に不安がある場合は、一度保険相談窓口等でプロに相談してみることをおすすめします。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。
本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。















