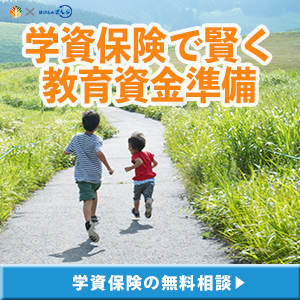学資保険の満期の設定はいつが最適か

学資保険を契約すると、毎月口座から引き落としで保険料を支払い子どもの教育資金を計画的に積み立てられます。
相続税を少しでも軽減するために、孫を学資保険の被保険者にする方法を選択する人もいますが、学資保険の満期はいつに設定するのがいいのでしょうか。
今回は、学資保険の満期時期のベストなタイミングについて詳しく紹介します。
満期金や祝い金などを受け取るときに発生する可能性がある税金についても、解説するので賢く学資保険の契約ができるようになります。
この記事は、次のような人におすすめの内容です。
- 学資保険の満期をいつにするか悩んでいる人
- 教育資金はどのタイミングで必要か知りたい人
- 満期金などの受け取り時に発生する税金が気になる人
それではまず、子どもの教育資金として用意しておきたい金額はいくらくらいなのか見ていきましょう。
目次
教育資金として貯蓄しておきたい金額とは
子どもを育てるために必要な教育資金は、子どもがどのような進路をたどるかによって大きく異なります。平成28年度に文部科学省が実施した調査「子供の学習費調査の結果について」によると、教育費の総額は次の通りです。
| 私立 | 公立 | |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 48万2,000円 | 23万4,000円 |
| 小学校 | 152万8,000円 | 32万2,000円 |
| 中学校 | 132万7,000円 | 47万9,000円 |
| 高校 | 104万円 | 45万1,000円 |
参考:http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/kekka/k_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/12/22/1399308_1.pdf
子どもが幼稚園から高校になるまでずっと公立であった場合の教育資金は約540万円になりますが、ずっと私立に行くと約1,770万円にもなります。
子どもの進路によって必要になるお金は最大で3倍以上も変わることが分かります。
また、近年は性別に関わらず大学に進学する子どもが増えているので、上記の教育資金にプラスして大学の費用も用意する必要があるでしょう。
生命保険文化センターの調査によると、私立大学の受験から入学までの費用は150万円~200万円が相場になっています(https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/education/7.html)。
大学にかかる費用の内訳については後ほど詳しく解説しますが、幼稚園から大学までの子どもの教育には非常にお金がかかると言えるでしょう。
教育費用の他にも子どもに与える食事や衣服、習い事の費用なども準備しなければいけません。
長期的に綿密な資金計画を立てるのはなかなか難しいため、学資保険を利用して子どもの教育資金を準備する人が多いのです。
ソニー生命の調査によると、2018年の学資保険の加入率は5割弱となっています(https://woman.mynavi.jp/kosodate/articles/2256)。
金融機関の口座を使った貯金で教育資金を準備する人もいますが、学資保険に加入すれば毎月決まった保険料を支払うだけで計画的に貯蓄ができるのでおすすめです。
それでは、学資保険の満期はいつにするべきかを見ていきましょう。
学資保険の満期はいつに設定する?おすすめのタイミングとは
学資保険は生命保険の一種であるため保険金を受け取る満期を設定する必要がありますが、学資保険の満期は被保険者である子どもの年齢で指定することになります。
子どもが中学や高校に入学するタイミングで満期に設定する人もいますが、一番多いのは大学入学前の18歳を満期にする人です。
満期を18歳にする人が多い理由は、大学に進学するためにたくさんの費用が必要になるからです。
大学進学には、受験費用や入学金の他にも予備校の費用なども支払う必要があります。生命保険文化センターの調査によると、私立大学を受験するために必要な費用は3万円~3万5,000円になっています。
2018年度の入学者選抜の受験料は次の通りです。
| 私立大 | 3万円~3万5,000円 |
| 国立大2次試験 | 1万7,000円 |
| センター試験(2教科以下) | 1万2,000円 |
| センター試験(3教科以上) | 1万8,000円 |
参考:https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/education/7.html
実家から通える範囲の大学に進学するなら心配する必要はありませんが、子どもが遠方の大学に進学を希望すれば新生活の準備金も用意しなければいけません。
自宅通学と自宅外通学にかかる費用の差をまとめたのが次の表です。
| 自宅通学 | 自宅外通学 | |
|---|---|---|
| 受験費用 | 24万7,100円 | 26万8,800円 |
| 敷金・礼金 | ‐ | 20万9,800円 |
| 家賃 | ‐ | 6万3,400円 |
| 生活用品費 | ‐ | 32万2,600円 |
| 大学への納付金(初年度) | 133万6,033円 | 133万6,033円 |
| 合計 | 158万3,133円 | 220万633円 |
参考:https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/education/7.html
ここまで説明したことから分かる通り、子どもが大学に進学するときは中学や高校に入学するよりも多額の費用が必要になります。
したがって、学資保険の満期を大学の入学前に設定することをおすすめします。
学資保険は満期金だけでなく、必要に応じて祝い金を付けられる保険商品です。
次の章では満期金にプラスして祝い金を付けることについて解説していきます。
祝い金はあった方が良い?
学資保険に満期金にプラスして祝い金を付ける場合、メリットとデメリットの両方があるので、一概にどのような人にも必要だとは言えません。
そもそも学資保険の祝い金とは、満期前に受け取れる保険金のことで株でいう配当のようなものです。
多くの人は学資保険の満期を大学入学前の18歳に指定しますが、子供の教育資金は中学や高校に入学・進学するタイミングでも必要になります。
学資保険に祝い金を付ければ、満期である18歳を迎える前にある程度まとまった教育資金を受け取れるということです。
満期金とは別に祝い金を付けるメリットは、据え置きができる点です。
祝い金が支払われるタイミングで受け取りの請求手続きをしなければ、祝い金を保険会社に据え置いて運用を継続できます。
保険会社に祝い金を据え置いておけば、預金利息よりも高い利息が付くだけでなく、いつでも引き出しができる教育資金をプールできます。
子どもの進路に柔軟な対応ができる点が満期金にプラスして祝い金を付ける最大のメリットと言えるでしょう。
一方、学資保険の満期金の他に祝い金を付けると返戻率が下がります。
なぜなら、祝い金なしの学資保険の方がまとまったお金を長期間にわたって運用できるため、受け取れる利息が多くなるからです。
また、学資保険によっては契約者の年齢が高いと払い込み免除特約が利用できないことがあるので注意しましょう。
学資保険に祝い金を付けないメリットについては先に少し触れたように、返戻率が高い状態で資金を運用できます。
保険商品によっては、祝い金の有無で返戻率に2%ほどの差が生じることがあるので、事前によく検討することが大切と言えるでしょう。
学資保険に祝い金を付けなければ、基本的に満期を迎えるまでに保険金を受け取れないため、貯金などで別途教育費用を準備する必要があります。
学資保険を解約すれば保険の契約期間に応じて解約返戻金が受け取れますが、学資保険は中途解約をすると元本割れをする可能性が高いのでおすすめできません。
学資保険の多くは祝い金を付けるか付けないかを選択できるので、事前に契約する保険に祝い金を付帯するプランがあるのかチェックすることをおすすめします。
今回紹介した祝い金のメリットだけでなく、デメリットも押さえた上で必要性を考えましょう。
注意!学資保険の保険金には税金がかかる
学資保険は基本的に受け取り時に税金はかかりませんが、場合によって課税対象になるので注意が必要です。
課税対象になるのは満期保険金だけでなく、お祝い金なども対象になるため事前に確認しておきましょう。
学資保険を受け取った場合に課税対象になるのは、次の3つのケースです。
- 学資年金の受け取りをしたとき
- 110万円超のお金を1年間で受け取ったとき
- 満期保険金や祝い金などが一時所得の控除額である年間50万円を超えたとき
学資保険の満期保険金や祝い金が課税対象になる3つのケースについて、順番に解説していきます。
学資年金の受け取りをしたとき
学資保険の種類によっては、満期金を年金方式で受け取れるものがあります。毎年定額の学資年金が受け取れますが学資保険の契約者が受取人である場合、雑所得の課税対象になります。
雑所得の課税金額は、次の計算式で算出します。
総収入額-収入額を得るために支出した金額
110万円超のお金を1年間で受け取ったとき
学資保険の保険料を払った人以外の人が、満期金などを受け取ると贈与税が課税されます。例えば、子どもの祖父が学資保険の契約者で保険料を支払っていて、受取人が子どもの母親に設定されていると贈与税が発生する仕組みです。
贈与税は1月から12月までの1年間の贈与総額に対して課税されますが、基礎控除が110万円あります。したがって、贈与税の計算式は次の通りです。
1年間の贈与総額-基礎控除(110万円)×贈与税率
上の計算に使用する贈与税における特例税率は、次の表の通りです。
| 基礎控除(110万円)後の 贈与税の課税価格 | 税率 |
|---|---|
| 4,500万円超 | 55% |
| 4,500万円以下 | 50% |
| 3,000万円以下 | 45% |
| 1,500万円以下 | 40% |
| 1,000万円以下 | 30% |
| 600万円以下 | 20% |
| 400万円以下 | 15% |
| 200万円以下 | 10% |
参考:https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm
満期保険金や祝い金などが一時所得の控除額である年間50万円を超えたとき
学資保険の満期金や祝い金を受け取った場合に、儲けの額が50万円を超えると課税対象になります。学資保険の保険料を満期まで支払う契約者が満期金の受取人になっていると一時所得が発生します。
一時所得の課税額の計算式は次の通りです。
総収入額-収入額を得るために支出した金額-特別控除(50万円)
上記の計算式を学資保険に当てはめると分かりやすくなります。
一時所得の金額=受け取った満期金・祝い金など-払込保険料-50万円
したがって、満期金や祝い金などが学資保険に払い込んだ保険料よりも多く、その金額が50万円を超える場合に税金を払う必要があります。とはいえ、学資保険の返戻率はそれほど高くないので、一時所得の金額が50万円を超える可能性はそれほど高くありません。
ただし、学資保険以外に一時所得の課税対象になる受取金がある場合は学資保険の満期金などの金額と合算して課税所得を出すので注意しましょう。
学資保険の満期金などを受け取るときに発生する税金は、保険契約者や受取人が誰になるかによって異なります。税金の種類や満期金などをいくらにするかによって税率が変わってくるので、学資保険を契約するときに考慮した上で賢い選び方をすることをおすすめします。
満期保険金・祝い金の受給時期の注意点
先に学資保険の満期を18歳に設定する人が多いと紹介しましたが、お金が必要になるタイミングと満期金や祝い金の受け取り時期が合っているか確認しておきましょう。
学資保険は被保険者が満期に設定した年齢になった場合に、最初に迎える契約応当日に保険金が受け取れる仕組みになっています。したがって、2月生まれの子どもを学資保険の被保険者にする契約を4月に結んだ場合、満期を18歳に設定していると満期金を受け取れるのは大学に入学した4月になります。
まとまった教育費用を準備する必要があるのは、大学に入学する前の高校3年生の時期であるにもかかわらず、上記の例ではお金がいるタイミングで学資保険の満期金を受け取れなくなるということです。今回の具体例で大学の入学費用を学資保険の満期金で準備したい場合は、満期を17歳に設定する必要があります。
以上のように、学資保険の満期保険金や祝い金の受給時期は本来お金が必要になるタイミングとずれている可能性があります。せっかく学資保険をかけたのに、満期金の受け取り時期がずれていると自己資金で対応することになるので学資保険の手続きをするときは特に注意してください。
学資保険の満期はしっかりチェックしておこう
学資保険は子どもの教育資金を賢く用意できる保険商品ですが、満期金の受け取り方法や祝い金の有無などについては自分で選択する必要があります。学資保険は契約者や受取人を誰にするかによって課税される税金の種類が変わってくるので、営業マンにすすめられるがまま学資保険を契約するのはおすすめできません。
ネットの学資保険の人気ランキングなどで、保険会社で実際に取り扱われている学資保険を確認するといいでしょう。
自分で確認するのが面倒だ、時間がないという方は、保険のプロに詳細を問い合わせることもおすすめです。「学資保険に興味があるが、満期時期の設定などがよくわからない」などと相談すれば、適した満期時期の設定方法からおすすめの学資保険まで紹介してくれます。
こちらから無料相談ができますので、ぜひご活用ください。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。
本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。