【年金手帳の基礎知識】使用場面・紛失時の手続き・正しい保管方法
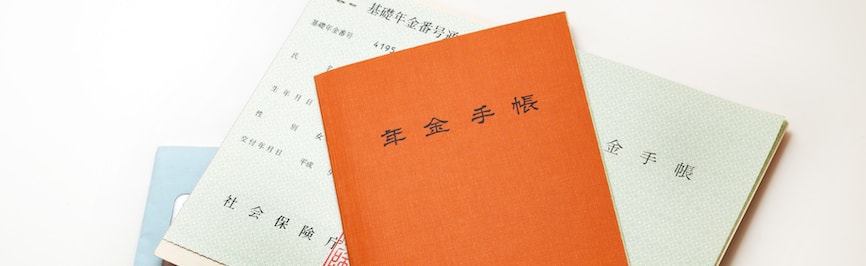
普段なかなか使用することのない年金手帳。いったどのような目的で何のために持っているのか疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。
また、年金手帳、そういえばどこにあるのかな…紛失してしまった…という人もいらっしゃるかもしれません。
そこでこの記事では、年金手帳の役割、各種変更届けや再発行の手続きの方法を詳しくご紹介していきます。
目次
年金手帳とは?年金手帳を使用する場面
「年金手帳」と聞いても、どのような用途で使用するのか、いつ必要になるのかピンとこない、という人も多いかもしれません。
そこで、まずは年金手帳についてご説明していきましょう。
年金手帳とは、日本年金機構より発行される冊子のことです。年金手帳の中身は主に、
- 個人情報
- 注意事項
- 国民年金の記録
- 厚生年金の記録
- 被保険者の届け出
から構成されています。
この年金手帳は、主に今までの年金加入状態を調べるとき、就職及び退職の手続きを行うとき、年金受給の手続きをするときに使用されます。
年金手帳には、茶色、オレンジ色、青色の3種類(が)あります。
茶色の年金手帳を受け取っているのは昭和35年10月から昭和49年10月に、国民年金の被保険者資格の手続きを行った人です。
昭和49年11月から平成8年12月までに手続きを行った人はオレンジ色、平成9年1月以降に手続きを行った人は青色の手帳を受け取っています。
平成8年12月までは国民年金、厚生年金、共済組合それぞれの公的年金制度ごとに手帳が発行され、それぞれの手帳に年金番号が記載されていました。そのため中には年金手帳を複数冊もっている人も多くいます。
しかし、平成9年1月以降、全ての年金で共有して使用できる「基礎年金番号」が導入され、年金手帳は「ひとり1つの番号」である、基礎年金番号が記載された青色手帳のみ交付されるようになりました。
年金手帳は、普段なかなか使用することはありませんが、年金を受給するまでずっと必要となる、とても大切な手帳です。
また、
- 入社及び退職、転職時
- 第三号被保険者への加入及び脱退
- 変更・申請。脱退など年金に関する届け出をするとき
- 年金の受給手続き及び相談時
- ねんきんネットへ登録するとき
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)に関する手続きを行うとき
に年金手帳は必要となります。
基礎年金番号とは?マイナンバーとの違い
さて、年金手帳の中で最も必要なもの、それは平成9年1月に導入された「基礎年金番号」です。
基礎年金番号は公的年金の加入者全員に与えられる共通の管理番号で、
4ケタ+6ケタの合計10ケタの数字でできており、原則としてその数字は一生変わりません。
基礎年金番号の主な役割は以下の3つです。
- 年金制度切り替え時の手続き忘れの発見及び未加入の防止
- 加入記録及び将来の年金見込額の通知
- 迅速かつ正確な年金の相談・裁定
つまり、基礎年金番号の導入により、我々の年金がより正確に管理されるようになった、ということです。
公的な手続きに使う番号と言えば、マイナンバーを連想する方も多いのではないでしょうか。
マイナンバーと (基礎年金番号)、混同されやすいのですが、実はまったく異なります。
一番大きな違いが、マイナンバーが「日本に住民票がある人全員」に付与されるのに対し、基礎年金番号は「公的年金制度の加入者」に付与されます。
ちなみに国民年金は、日本に住民票を持っている20歳以上かつ60歳未満の人は全員加入しなければならないので、
対象者は全員所持している、ということになります。(しかし、20歳未満で就職し、厚生年金に加入した人はその時点において基礎年金番号が付与されます)。
さらに、基礎年金番号は年金専用の管理番号ですが、マイナンバーは年金を含めた広範囲の行政サービスの情報管理をスムーズに行うために使用される番号です。
つまり、マイナンバーの方が、利用対象も付与の範囲もより大規模である、ということです。
平成30年3月より、基礎年金番号とマイナンバーの連携が開始されました。
このことにより、今まで基礎年金番号のみでしか手続きすることができなかった年金関連の手続きが、マイナンバーでも行えるようになりました。
だからといって基礎年金番号が不要になった、というわけではありません。
海外への転出、口座振替の申し込みは基礎年金番号でしか行えませんので、年金手帳は大切に保管しておく必要があるのです。
結婚などで年金手帳の氏名・住所変更は必要?
結婚や転居などで住所や氏名が変わった際、変更届を出さなかったからと言って何か罰則があるわけではありません。
なぜなら公的年金は氏名ではなく基礎年金番号で管理されているからです。
しかし、年金手帳を紛失してしまった場合などの手続きの際に本人確認に現住所や氏名が必要になる場合があります。
もし変更していなかった場合、本人確認に手間をとるばかりか、最悪の場合本人確認ができない…というケースも起こりうるので、
住所や氏名が変わった場合は速やかに変更の手続きを行っておく方が賢明です。
ここでは国民年金、厚生年金及び共済組合の手続き方法をそれぞれご紹介いたします。
国民年金の手続き
現在国民年金に加入しており、結婚後も国民年金に継続して加入する、という方は自動で手続きが行われるので、とくに届け出は必要ありません。婚姻届が提出された際に本籍が移動となると同時に新しい名字が自動的に年金記録に反映されます。
また、住所も住民票の移動届を提出したと同時に新しい住所が年金記録に反映されるので、取り立てて手続きは必要ありません。
ひとつ注意したいのが、手続きが完了するまでに2ヶ月ほどの時間を要すること。
そのため、引っ越しをする際は必ず郵便物の転送の手続きを取るようにしましょう。
手続きをしないと、年金定期便等年金事務所からの書類が受け取れなくなってしまいます。
また、年金手帳の氏名変更は、自分で記入するようになるので、忘れずに記入するようにしましょう。
健康保険(協会けんぽ)・厚生年金の手続き
勤務先で健康保険(協会けんぽ)に加入しており、結婚後も引き続き健康保険(協会けんぽ)・厚生年金に加入する、という人は氏名、住所それぞれに変更手続きが必要になります。
まず、結婚後に名字が変わる場合は勤務先に年金手帳と被保険者氏名変更届を提出します。
その後は勤務先が変更届を年金事務所に郵送してくれるのでこれで手続きはすべて完了です。
年金手帳の氏名変更は基本的には担当の部署で新しい名字を記載するようになっていますが、会社によっては自分で記載する場合もあります。この際、自分で手帳に記載しても、何も問題はないので心配はいりません。
氏名と同時に住所も変更になる場合は被保険者住所変更届もあわせて提出します。被保険者氏名健康届・被保険者住所変更届は勤務先で配布されるか、もしくは協会けんぽのホームページからダウンロードすることができます。どちらの書類も基礎年金番号が必要になるので、記入の際は年金手帳を忘れずに準備しておきましょう。
配偶者の扶養に入る場合
最後に配偶者の扶養に入る場合の手続き方法をご紹介しましょう。配偶者が国民年金に加入している場合は、特に手続きは必要ありません。
健康保険(協会けんぽ)・厚生年金に加入している配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先で「国民年金第3号被保険」の届け出が必要になります。届け出の方法は会社によって異なりますが、主に、
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 戸籍謄本もしくは住民票(提出日より90日以内に発行されたもの)
- 原則年間収入130万円未満であることを確認できる書類
- 本人および配偶者の年金手帳
- 本人の健康保険証
が必要になります。
年金手帳を紛失した場合と再発行の方法
なかなか出番のない年金手帳。いざ必要となったときに、どこにしまったかわからなくなった、
紛失してしまった…というのもよくある話です。
年金手帳を紛失してしまったら、退職や転居、氏名変更等の各種手続きが行えなくなってしまいます。また、年金の裁定請求を行うことができなくなる可能性もあるのです。このように、年金手帳を紛失してしまうと、さまざまな不具合が生じてしまいます。
そこでここでは、年金手帳を紛失した場合にどうすればよいかをご紹介していきましょう。
再発行の方法
年金手帳を紛失もしくは棄損してしまった場合は、再発行することが可能です。
被保険者が「年金手帳再交付申請書」にマイナンバーもしくは基礎年金番号を記載して提出すれば手続きは完了。
ただし再発行の手続き場所は、年金の種類によって異なります。
国民年金の場合は住所地の市区町村役場、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金の場合は年金事務所が手続き先となるので注意しましょう。手続きの方法は電子申請、郵送、窓口持参の3種類、棄損の場合は古い年金手帳を添付しなければなりません。年金手帳の再交付は原則として郵送となっています。
場合によっては即日発送も可能
緊急の場合は申請者本人が必要な書類を持って年金事務所の窓口に行けば、即日発行も可能です。即日発行に必要な書類は以下の通りです。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 基礎年金番号もしくはマイナンバー
- 年金手帳再交付申請書
年金手帳を即日発行してもらう場合、原則として本人が手続きを行わなければいけませんが、
- 社会保険労務士及び社会保険労務士の代理人
- 法定代理人
- 事業主及び事業主の代理人(事業主を通じて申請書が提出された場合)
が代理人となった場合に限り、本人以外でも手続きを行うことができます。通常の代理人でも、委任状があれば手続きは行えますが、この場合は即日発行ではなく後日郵送という形になるので気をつけましょう。
また、覚えておいてほしいのは「再発行された年金手帳は後日郵送が原則。即日発行する、といったルールは存在していない」ということ。
つまり、即日発行されるケースもあるが、即日発行が可能かどうかは窓口の担当者の判断によるので、即日発行が拒否されるケースも大いにある、ということ。また、即日発行が拒否されたからといってクレームを申し出ることはできません。なぜなら日本年金機構が定める規定は「即日の再発行は行わない」となっているからです。
【年金手帳の保管方法】年金手帳は会社が保管する場合もある?
原則として年金手帳は被保険者本人が保管することとなっています。
しかし、会社が年金手帳を保管している、というケースも多いのが現状です。会社が年金手帳を補完するメリットは大きく分けて2つあります。
まず1つ目は、紛失のリスクを減らせること。年金手帳はあまり出番がないため、個人で保管していると紛失してしまうことが多々あります。
もし従業員が年金手帳を紛失してしまった場合、会社が年金手帳の再発行手続きを行うケースがほとんどです。
従業員を何千人も抱える大企業では特に、就職及び退職の際に複数人から「年金手帳を失くしました」と言われてしまったら、
再発行の手続きだけでかなりの労力を要します。
このムダを省くため、会社で保管…というケースが多くなっているのです。
もうひとつのメリットは住所や氏名変更の手続きがスムーズに行える、ということ。
従業員が結婚、引っ越しなどで住所や氏名が変更になった場合、会社はその従業員に変わって住所や氏名変更を代行しなければなりません。
その際、もし年金手帳を個人で保管していたら、会社が従業員に年金手帳を持ってくるよう指示して、
もし紛失していれば再発行の手続きをして…とひと手間もふた手間もかかってしまいます。
その点、会社が保管しておけば、従業員から申し出があった時点で速やかに変更の手続きを行うことができるのです。
しかし、会社が年金手帳を保管することで、会社が手帳を紛失してしまうというリスクや退職時に手帳の返却を忘れてしまう、というケースも考えられます。
本来であれば、年金手帳は個人で保管する必要があります。
厚生年金保険法施行規則第十六条にも「事業主は提出された年金手帳を確認したあと、手帳は被保険者に返付しなければならない」と記載されてあります。
しかし、手続きをスムーズに行うため、ムダな労力を使わないようになど、さまざまな理由から会社が年金手帳を保管しているケースも少なくないのが現状なのです。
年金手帳はしっかり保管を
年金手帳は将来年金に関するさまざまな手続きを行う際に大切なものです。
いざ必要となったときにどこにあるかわからない…ということがないように、普段からしっかりと管理しておくようにしましょう。
また、公的年金以外に、年金の積み立てをしたい、と思った場合はまず個人年金保険が思い浮かぶ人も多いでしょう。
年金に関するさまざまな疑問、質問が生じたときは、保険の専門家に相談することをおすすめします。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。
本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。













