個人年金保険には入るべき?保険の種類・特徴・控除の仕組みと注意点
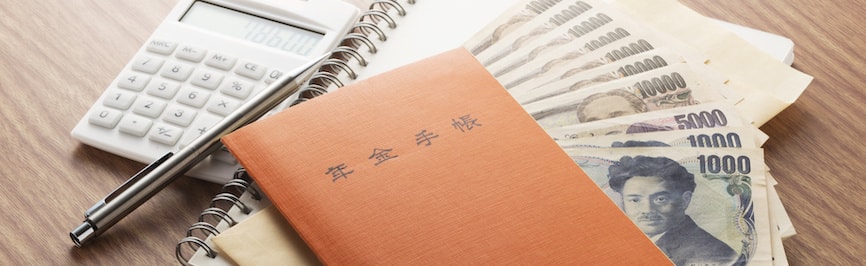
老後の備えは十分だと自信をもって言えますか?個人年金保険は、老後の資金を豊かにするための一つの手段です。今回は、その個人年金保険の種類や特徴、控除の仕組みなどを詳しくご紹介します。
目次
個人年金保険とは?国民年金や厚生年金だけではだめ?
個人年金保険とは、公的年金では補えない老後の資金を自分で準備するためのものです。では、公的年金とはどんなものなのでしょうか。まずは、二種類ある日本の年金制度からご説明します。
公的年金
国が管理や運営をしているもので、国民年金、厚生年金などのことを言います。
国民年金とは、日本に住む20歳から60歳の全ての人が加入しなければいけません。これに加入していることで、65歳から生活の扶助としてお金が支給されたり、障害者認定をされた時に保障されたり、死亡した時に、遺族に年金が支給されたりするのです。
厚生年金とは、会社員や公務員などの、この制度の適用を受けている会社に勤めている人が加入しなければいけないもの。自営業の人は、基本的には国民年金のみの加入ですが、会社員や公務員は両方に加入しているため、老後に受け取れる金額が多くなるという仕組みになっています。
私的年金

国以外の民間の会社などが管理や運営をしているものです。
老後にゆとりのある生活を送るためには、国民年金や厚生年金などの公的年金の加入で受け取れる金額だけでは、赤字になる家庭もあります。厚生労働省が公表した2017年度の年金受給額は、夫婦二人世帯で月額約22万円、年収にすると約265万円です。
しかし、同年度の平均年収は約432万円。公的年金の加入だけで受け取れる金額では、生活が苦しくなることが分かります。この公的年金の金額で補えない部分を、個人で選択して加入するものが私的年金と呼ばれています。個人年金保険は、この中に分類されるのです。
加入するメリットとデメリット
メリットとしては、20歳から60歳までの人であれば、誰でも加入することができること。自動で積立していく商品のため、お金は確実に貯まっていきます。また、多くの会社が、さまざまな商品を販売しているため、自分に合ったものを選ぶことができるでしょう。さらに、税金の控除を受けられるというメリットも。これについては、後程詳しく解説をします。
デメリットとしては、民間の会社が取り扱っている商品のため、もしその会社が倒産をしてしまえば、受け取りができなくなるというリスクがあります。また、途中で解約をしてしまうと、解約返戻金は支払った金額を下回るため、損をしてしまう可能性があります。
個人年金保険の種類と特徴
様々な種類がある個人年金保険。積立の方法や受け取り期間など、それぞれの特徴を詳しくご紹介します。
終身

加入をすると、契約者本人が亡くなるまで年金を受け取ることができる商品です。生きている間は、受け取り期間が無期限ということだけあり、支払う金額は高額であることが特徴としてあります。もし契約者本人が早く亡くなってしまった場合は、損をしてしまうリスクがあるでしょう。
万が一のことを考えて、この商品は5、10、15年と保証期間を設定することができます。もし設定した保証期間内に契約者本人が亡くなってしまった場合は、遺族が年金を受け取ることができるのです。
確定
契約時に、契約者本人が確定した一定の期間内で年金を受け取ることができるものです。契約の期間内であれば、生死に関係なく定額の金額が支給されるので、安定していることが特徴的。先ほどご紹介した終身型に比べると、支払う保険料は安いでしょう。しかし、長生きをして確定した期間を越えてしまった場合は、受給が終了してしまうというリスクがあります。
変額

給付金額が確定していないことが特徴の商品。一時払いで払い込んだ保険料を運用し、その成果によって、将来受け取れる金額や解約返戻金、死亡給付金の額が変わります。運用が上手くいかなければ、一時払いで払い込んだ金額を下回ってしまうというリスクがあるでしょう。
しかし、もし運用期間中に、契約者本人が亡くなってしまった場合は、払い込んだ金額以上の金額は保障されています。また、受け取り期間や受け取り方法は、契約者本人が自由に選択できるという特徴も。
外貨建て
円ではなく、ドルやユーロなどといった外貨で運用する商品のことを言います。受け取る金額や死亡保障の金額は、外貨ベースであるため、為替の変動によっては損をしてしまう可能性があるでしょう。また、円を外貨に交換する手数料もかかります。
しかし、受け取りの際は、外貨のまま受け取ることもできるため、海外旅行の予定がある場合や海外移住の予定がある場合は有利なことがあります。支払い方法は、取り扱っている会社によっては、一時払いの場合と定期的に払う場合とで選ぶことができるようです。
上手な運用のためには、海外の経済や為替を常にチェックしておく必要があるので、他の商品よりも負担は少し大きいかもしれません。
個人年金保険料控除で税金の負担を軽減できる?
先ほど、個人年金保険に加入するメリットとしてもご紹介しましたが、所得控除の対象の商品であるため、税金の負担を軽減することができます。
生命保険料控除の一つ

所得税を算出する際に、収入から必要経費を差し引く所得控除という制度があります。個人年金保険は、この所得控除の対象となり、「生命保険料控除」という項目に当てはまるのです。
この項目には、死亡保険や医療保険などの「一般の生命保険料」と、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」があります。仕組みとしては、支払った一定の金額が、所得額から差し引かれます。税金の対象となる所得の総額が減るため、税金が安くなるのです。
個人年金保険料控除の条件
控除の適用を受けるためには、「税制適格特約」が付いていなければいけません。この特約を付けるためには、いくつか条件があるので、加入の際には気を付けましょう。
- 加入している保険の受取人が本人または配偶者であることが必要
- 払い込み期間が10年以上であること必要
- 確定年金の場合、受け取り開始年齢が60歳以上、受け取り期間が10年以上であることが必要
所得控除を受けるためには申告が必要

個人年金保険料控除を受けるためには、申告をする必要があります。会社員・公務員の人は、年末調整の時期に、保険料として支払った金額を書類に記入して提出しましょう。この時に、保険会社から送られてくる証明書も一緒に提出する必要があります。自営業の人は、2月中旬から行われている確定申告で手続きをしてください。この場合も、保険会社から送られてくる証明書の提出が必要です。
控除額の計算方法
個人年金保険料控除額は、年間払込保険料額によって計算されます。ただ、この計算方法には旧制度と新制度があることを知っておきましょう。契約や更新をした時期が2011年の12月31日以前であれば旧制度、それ以降の契約や更新の場合は新制度での計算となります。
それぞれの制度で控除額の計算方法が異なるため気を付けてください。例えば、新制度で払い込みが年間で20,000円以下の場合、所得額から払い込んだ金額の全額が差し引かれることになります。20,000円以上40,000以下の場合は、払い込んだ金額の1/2に10,000円をプラスした金額が控除されるでしょう。
※控除額の補足:【個人年金保険料の控除額】控除を受けられる条件と税制上の注意点
個人年金保険を選ぶときの注意点
個人年金保険は、長期に渡る契約であるため、加入の際は慎重に選ぶ必要があるでしょう。では、どんなことに注意をすると良いのでしょうか。詳しくご説明します。
受け取り時に税金がかかる

個人年金保険料の受け取りの際には、税金がかかることを知っておきましょう。かかる税金の種類は、契約者と受取人の両方が加入した本人の場合、契約者が本人で受取人が配偶者などである場合とで変わります。
前者の場合は、年間の年金受け取り総額から必要経費を引いた部分が、所得税や住民税などの課税の対象となるでしょう。
後者の場合は、契約者本人が配偶者に、年金の受け取りの権利を贈与したと考えられます。そのため、初年度は贈与税がかかってしまうのです。ただし、初年度は所得税や住民税などの課税の対象にはなりません。2年目以降は前者の時と同じように、年間の年金受け取り総額から必要経費を引いた部分が、所得税や住民税などの課税の対象となり、税金を支払うことになるでしょう。
配偶者控除が受けられなくなることも
受け取る年金は、所得として換算されます。そのため、もし配偶者控除の対象となっている妻が、個人年金保険を受け取るようになると、その金額によっては配偶者控除としての対象から外れてしまうという可能性が出てくるでしょう。さらに、妻は受け取る年金に対して所得税などを支払わなければいけなくなります。加入の際は、受け取りの際のこともしっかりと考えて契約をする必要があるでしょう。
契約途中の解約は損をする

個人年金保険に加入するデメリットでも少し触れましたが、途中で解約する場合は、損をしてしまう可能性があります。基本的に、契約した個人年金保険を解約する際は、解約返戻金を受け取ることができるでしょう。しかしその金額は、実際に支払った金額よりも下回ってしまうのです。特に注意しなければいけないのが、契約してから3年目くらいまで。解約返戻率がかなり低く設定されているので、この期間に解約をしてしまうと、大幅に損をしてしまうことになるでしょう。
利率はあまり高くない
実は、個人年金保険の利率はあまり高くありません。そのため、契約したからと言って、お金が大幅に増えるというわけではないことを知っておきましょう。老後の生活を少しでも豊かにするためのものと考えておいてください。
支払い回数が少ない方がお得
支払いの方法は、回数が少ない方がお得でしょう。可能であれば、契約時に保険料を前納すること。前納割引が適用されるため、保険料が安くなる場合があります。前納が難しい場合は、月払いにするより年払いにして、支払う回数を減らしましょう。受け取る金額が変わらない場合、回数が少ない方が支払い総額は安くなることがあります。
受け取り開始は60歳から

受け取りの開始時期が60歳からであるものがほとんどです。これは、59歳以下での受け取り開始にしてしまうと、個人年金保険料控除の対象から外れてしまうからです。税金の控除が受けられないと、加入するメリットが一つなくなってしまうので気を付けてください。
受け取り開始を遅らせるとお得になることも
公的年金は、受け取り開始の時期を遅らせることで、金額を上げることができます。それと同様に、個人年金保険も、受け取り開始時期を遅らせることによって、貰える金額が増える場合があります。契約の際は、この点も検討の材料とすると良いでしょう。
クレジット払いができるかどうか
個人年金保険を取り扱っている会社によっては、支払い方法にクレジットカード払いを選択できるところがあります。クレジットカード払いにすることで、ポイントを貯めることができる場合もあるでしょう。長期の契約であるため、金額も大きいものが多いです。少しでもお得になる方法を選択することをお勧めします。
払い込み期間は10年以上に
個人年金保険料控除を受けるための条件でもご紹介しましたが、税金の控除を受けるためには、払い込み期間を10年以上にしなければいけません。契約の際は、この払い込みの期間にも注意する必要があります。
年金保険に悩んだら保険の専門家に相談

ファイナンシャルプランナー
個人年金保険は、少し複雑で専門的な知識が必要な商品です。そのため、どこの会社で契約するのか、どの種類を契約するのかなどに悩んだら、ファイナンシャルプランナーに相談しましょう。ファイナンシャルプランナーは、保険と家計の専門家です。的確なアドバイスを貰えることが多く、安心して契約ができるでしょう。
無料保険相談サービス
無料保険相談サービスを利用して、まずは気軽に個人年金保険について相談することもお勧めです。総合の保険代理店であれば、複数の会社の商品を取り扱っていることが多いため、ライフプランに合わせて提案をしてくれるでしょう。
【まとめ】老後の備えに個人年金保険を!
個人年金保険について、知識を深めていただけましたか?老後の備えをしながら、節税対策ができる保険なので魅力的な商品です。ただ、支払い金額や期間に注意することと合わせて、受け取り時の税金のことにも注意する必要があります。複雑な保険でもあるので、専門家に相談することで、自分にあった個人年金保険を選びましょう。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。
本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。













