貯蓄型の生命保険の特徴は?おすすめの保険の傾向を解説
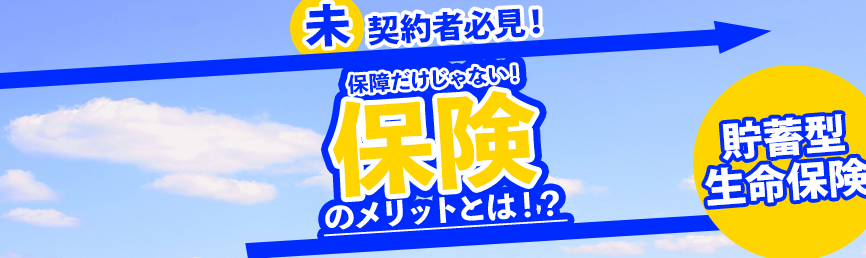
生命保険にはいくつか種類がありますが、その中でも貯蓄性を備えている保険もあります。
「保障と同時に貯蓄もできるので一石二鳥!」という面もありますが、果たして本当におすすめなのか気になるところです。
そこで今回は、貯蓄型保険の特徴や種類、メリット・デメリットを中心に、掛け捨て型保険や銀行貯金との違いについても詳しく解説していきます。

- 貯蓄型保険には、終身保険、養老保険、学資保険、個人年金保険などがあり、将来必要になるお金を保障を付けながら準備できる特徴がある
- ライフイベントに合わせてお金を貯められるので、貯金が苦手な人でも続けやすい
- 掛け捨て型保険や銀行貯金と比較されることが多いが、それぞれの特徴やメリット・デメリットをしっかりと理解したうえで保障と貯蓄のバランスの取れるものを選ぶのがおすすめ
- 貯蓄型保険の相談は、無料で何度でも専門家に相談できる保険相談窓口がおすすめ!
| 保険は賢く専門家に無料相談! |
 |
| 40社以上の保険会社と提携! 複数の保険商品をまとめて比較できる |
| 相談員のFP取得率100%! これからの資産運用全般を相談できる |
| 相談料は完全無料! 繰り返し何度も相談できる |
| 無料相談で豪華プレゼント! お米や牛肉などがもれなくもらえる |
貯蓄型保険とは?
まずは、貯蓄型保険とはどのような保険のことを指すのか確認していきましょう。
併せて「貯蓄型保険は不要・無駄」と言われる理由やその対策法についても解説していきます。
貯蓄型保険は「保障」と「貯蓄」を備えた保険
貯蓄型保険とは、保険料を支払うことで「保障」と「貯蓄」を同時に備えられる保険のことをいいます。
保険会社は、支払われた保険料のうちの一部を積み立てて運用し、将来の満期保険金や解約返戻金の支払いに充てます。
契約者は、ライフイベントに合わせて満期日を設定したり解約のタイミングを図ったりすることで、必要な資金を準備しておくことができます。

なお、こういった具体的な貯蓄型保険の活用法は後程詳しく解説します。
貯蓄型保険が不要・無駄といわれる理由と3つの対策
貯蓄型保険は、ひとつでふたつの機能があるためお得な保険商品と考えられますが、一方で「貯蓄型保険は不要・無駄」という考えもあります。
不要といわれる主な理由のひとつに「返戻率(※)の低さ」がありますが、近年の低金利のあおりを受けて貯蓄型保険の運用益が期待できずに、以前よりも返戻率が低い状態が続いています。
そのため、投資信託といった積極的な資産運用をすすめる考えもありますが、投資信託はハイリスクハイリターンな商品もあり、元本割れリスクが伴います。


そこで、貯蓄型保険の返戻率を高くするポイントをご紹介します。
※返戻率:支払った保険料に対していくら解約返戻金があるかを示す。「解約返戻金÷払込保険料総額×100」で求める。
貯蓄型保険の返戻率を高くするポイント
貯蓄型保険の返戻率を上げるポイントは以下の3つです。
ポイント
- 保険料を一括払い(前納)する
- 保険料を短期払いにする
- 月払いから年払いに変更する
これから貯蓄型保険に加入する方で資金に余裕のある方は、保険料を一括払い(前納)すると、保険料総額が通常よりも少額になるため、結果として返戻率を上げることができます。
しかし、まとまった資金がない場合は無理せずに、保険料を短期払いにする方法を検討してみましょう。
たとえば、20年満期の貯蓄型保険を10年で払込み完了すると、保険料が割引されて返戻率を上げることにつながります。ただし、毎回の保険料は高額になるため家計の負担にならないように注意しましょう。
また、すでに契約しており月払いで保険料を支払っている方は、年払いに変更することを検討してみましょう。

貯蓄型保険は主に4種類に分けられる
貯蓄型保険にはさまざまな商品がありますが、その中でも代表的な以下の4つの保険をご紹介していきます。
- 終身保険
- 養老保険
- 学資保険
- 個人年金保険
それぞれについて見ていきましょう。
終身保険
保険料は契約時から一定のままで更新がなく、一生涯同じ保険料となります。そのため、病気やけがのリスクの少ない若いときに加入するほど、保険料は安くなります。
しかし、貯蓄性があるため、掛け捨てタイプの保険よりも保険料は高額になります。


もちろん、一生払い続けるタイプもありますが、保険料の払い込みを60歳や65歳までとしたり、10年や20年で払い切るとしたりできるタイプもあります。
保険料の払込期間を短くして納めてしまったほうが、運用益がついて解約返戻金をより多くもらえる可能性があります。
保険料を抑えたいなら「低解約返戻金型終身保険」
終身保険の中には、「低解約返戻金型終身保険」という商品があります。
通常の終身保険よりも保険料が割安なうえに、一定期間後にまとまったお金を受け取れます。
ただし、低解約返戻期間中に解約してしまうと、返戻金が少なく元本割れしてしまう可能性が高いので、解約するタイミングには注意が必要です。
養老保険

死亡保険金と満期保険金は同額という特徴があり、満期保険金をもらうと保障もそこで終了します。
保険期間中に中途解約をすることもできますが、ほとんどのケースで元本割れしてしまいます。
そのため、満期まで寝かせておけるだけの余剰資金を一括払いして、保障と貯蓄を兼ね備えるという利用方法が一般的です。
ただし、近年の低金利下では、満期までおいても返戻率が100%を超えないことも多く、以前のバブル期のような魅力的な返戻率のときと比べると、加入するメリットは少ないといえます。
学資保険
学資保険の多くには、契約者(一般的に親)に万が一のことがあった場合、それ以降の保険料の払い込みが免除されるという特徴があります。
その場合でも、もちろん祝い金や満期金は契約通りもらえますので、子どもの教育資金に備えることができます。
学資保険は、子どもが18歳や20歳、22歳などに達するときに満期日を設定し、満期に合わせて保険金を受け取れます。
また、小・中・高の各入学年度に合わせてお祝い金がもらえるように設定することもできます。

個人年金保険

個人年金保険は、年金の受け取り方によって、「有期年金」「確定年金」「終身年金」の3つに分けられます。それぞれの特徴を簡単にご紹介します。
有期年金
被保険者(年金受取人)が生存している場合に限り、一定期間年金を受け取ることができます。
被保険者が死亡してしまと、原則として年金の支給は終了しますので、死亡するタイミングによっては、払い込んだ保険料よりも受け取る年金が少なくなる可能性があります。
確定年金
被保険者の生死にかかわらず、一定期間年金を受け取ることができます。
被保険者が死亡した場合、遺族に年金が支払われるので損するということがありません。
終身年金
被保険者が生存しているうちは、一生涯年金を受け取ることができます。
被保険者が亡くなった時点で年金の支給が終わるので、早期に亡くなってしまうと元本割れしてしまう可能性があります。

貯蓄型保険のメリットとデメリット
貯蓄型保険にはどのようなメリットとデメリットがあるのか、それぞれ確認していきましょう。
貯蓄型保険のメリット
貯蓄型保険には、主に以下のようなメリットがあります。
- 払込保険料よりもらえる保険金の方が多いことがある
- 将来のライフイベントに備えられる
- 貯金が苦手な方でも自動的に貯蓄ができる
- 「自動振替貸付」「契約者貸付」が利用できる
それぞれについて見ていきましょう。
払込保険料よりも受け取れる保険金の方が多いことがある
貯蓄型保険の種類にもよりますが、中途解約する際にもらえる解約返戻金や満期時に受け取れる満期金が、払い込んだ保険料よりも高額になることがあります。
養老保険や個人年金保険などを中途解約すると元本割れする可能性がありますが、終身年金であれば解約するタイミングによって元本割れリスクを負わずに払い込んだ以上の解約返戻金を受け取ることもできます。
将来のライフイベントに備えられる
貯蓄型保険は、それぞれライフイベントに必要なまとまった費用を準備するために利用されます。

もちろん、貯蓄だけでなく保障も付いているので万が一の場合でも安心です。
貯金が苦手な方でも自動的に貯蓄ができる



気づけば必要な時期に必要なお金が貯まっているので、貯蓄方法のひとつとして有効です。
「自動振替貸付」「契約者貸付」が利用できる
どちらも借入ということになるので利息を含めた返済が必要になるうえ、返済できなかった場合、満期金から相殺して返済することになります。
貯蓄型保険のデメリット
一方、貯蓄型保険には以下のようなデメリットがあります。
- 早期解約は元本割れリスクがある
- 固定金利型はインフレに対応できない
それぞれについて見ていきましょう。
早期解約は元本割れリスクがある
貯蓄型保険を早期解約する場合、解約返戻金はほとんど受け取ることができません。
保険会社では、支払われた保険料の一部を満期金や解約返戻金を支払うための原資として積み立てますが、早期解約をしてしまうと資金がまだ貯まっておらず返戻金として支払う分が準備できないのです。

固定金利型はインフレに対応できない
固定金利型の貯蓄型保険は、契約時の金利に固定されるので、満期金の受取時にインフレが起きているとお金の価値が目減りし、必要なお金が準備できないというリスクがあります。
インフレリスクを回避するには、変額タイプや外貨建ての貯蓄型保険に加入するのもひとつの方法です。
貯蓄型保険と掛け捨て型保険の違い・おすすめな人
貯蓄型保険と掛け捨て型保険の違いについて、以下にまとめました。
【貯蓄型保険と掛け捨て型保険の比較】
| 貯蓄型保険 | 掛け捨て型保険 | |
| 保険料 | 割高 | 割安 |
| 満期金 | もらえる | なし |
| 解約返戻金 | もらえる | 一般的になり(返戻金がある場合もあるが少額) |
| 保険の種類 | 終身保険、養老保険、学資保険、個人年金保険など | 定期保険、医療保険、がん保険、収入保障保険など |
| 加入目的 | 保障も付けつつ将来の必要な出費に備えるため | 安い掛け金で万が一に備えるため |
このような比較を踏まえると、「貯蓄型保険が向いている方」と「掛け捨て型保険が向いている方」の特徴が見えてきます。
貯蓄型保険がおすすめな人
貯蓄型保険がおすすめなのは、以下に挙げる人です。
- 支払った保険料を無駄にしたくない人
- 保険で保障と貯蓄の両方を備えたい人
- 一生涯の保障を付けておきたい人 など
保険料をムダにしたくない人
貯蓄型保険は、支払った保険料の一部が積み立てられるので、満期時に「満期保険金」を受け取れたり、中途解約をしたときに「解約返戻金」を受け取れたりします。


保障と貯蓄を兼ね備えたい人
貯蓄型保険は、満期保険金や解約返戻金、お祝い金などを受け取れるので、ライフイベントに合わせて貯蓄にも生かせます。
特に学資保険や個人年金保険などは、子どもの教育費やご自身の老後資金の確保のためなど、明確な目的があることがほとんどなので、保障を得つつも貯蓄に生かしたい人におすすめです。
一生涯の保障を付けておきたい人
一生涯の保障が得られる「終身保険」は貯蓄型保険であることがほとんどです。

掛け捨て型保険がおすすめな人
一方で、掛け捨て型保険がおすすめなのは以下に上げる人です。
- 保険料を安く抑えたい人
- 定期的に保障の見直しをしたい人
- ほかの方法で貯蓄をしている人 など
保険料を安く抑えたい人
掛け捨て型保険の大きなメリットには、「保険料が割安」ということがありますが、シンプルに必要な保障だけを付けたいという人には掛け捨て型保険がおすすめです。
特に、家庭を持ち子どもが生まれてお金がかかる世代の人は、保険料の支払い負担が大きくなりがちです。
そこで、子どもが独立するまでの期間を掛け捨て型保険に加入することで、安い保険料で大きな保障を付けることができます。

定期的に保障の見直しをしたい人
掛け捨て型保険は、解約しても保険料の戻りがなく「解約返戻率」を気にする必要がないので、解約するタイミングに制限がありません。

貯蓄は保険以外の方法で取り組んでいる人
「貯蓄と保険は別々に行っている」という人も、掛け捨て型の保険がおすすめです。
貯蓄の方法には、保険だけでなく金融機関の預貯金や投資信託などさまざまな方法がありますので、いずれかの方法ですでに貯蓄をしている人は保険で備える必要性は少ないといえます。
保険相談窓口おすすめ3選
貯蓄型保険の相談は、無料で何度でも専門家にアドバイスがもらえる保険相談窓口がおすすめです。以下、おすすめ保険相談窓口を厳選して3つ紹介します。
ほけんのぜんぶ

- 相談員のFP取得率100%※1
- 相談手数料完全無料
- 取扱保険会社数40社以上
- 47都道府県相談対応可
- 無料相談でお米や牛肉などのプレゼントがもらえる

| 取扱保険会社数 | 40社以上 |
|---|---|
| 対応地域 | 47都道府県 |
| 相談方法 | オンライン・訪問 |
| キャンペーン | あり |
| 相談員の特徴 | 350名以上のFPが在籍 |
マネーアドバンス

- FP取得率100%※1
- 相談料0円
- 相談実績10万件以上!
- 350名以上のFP在籍
- 無料相談でお米や牛肉などのプレゼントがもらえる

| 取扱保険会社数 | 40社以上 |
|---|---|
| 対応地域 | 47都道府県 |
| 相談方法 | オンライン・訪問 |
| キャンペーン | あり |
| 相談員の特徴 | 350名以上のFPが在籍 |
マネードクター

- 相談料無料
- 提携保険会社数40社以上
- 年間20万件以上の相談実績
- 電話・フォームで予約可能
- 全国に145拠点

| 取扱保険会社数 | 41社 |
|---|---|
| 対応地域 | 全国 |
| 相談方法 | オンライン・訪問 |
| キャンペーン | あり |
| 相談員の特徴 | 全国約2,200名のFPが在籍 |
まとめ
今回は、貯蓄型保険の特徴や種類、メリット・デメリットを中心に、掛け捨て型保険や銀行貯金との違いについても詳しく解説していきました。
貯蓄型保険には、終身保険、養老保険、学資保険、個人年金保険などがあり、将来必要になるお金を保障を付けながら準備することができます。
ライフイベントに合わせてお金を貯められるので、貯金が苦手な人でも続けやすいです。
また、掛け捨て型保険や銀行貯金といったものと比較されることが多いですが、それぞれの特徴やメリット・デメリットをしっかりと理解したうえで保障と貯蓄のバランスの取れるものを選ぶことをおすすめします。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。
本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。













